記事公開日
最終更新日
【富裕層だけの話じゃない】相続税で破産?世界の常識と日本のヤバい現実を徹底解説!
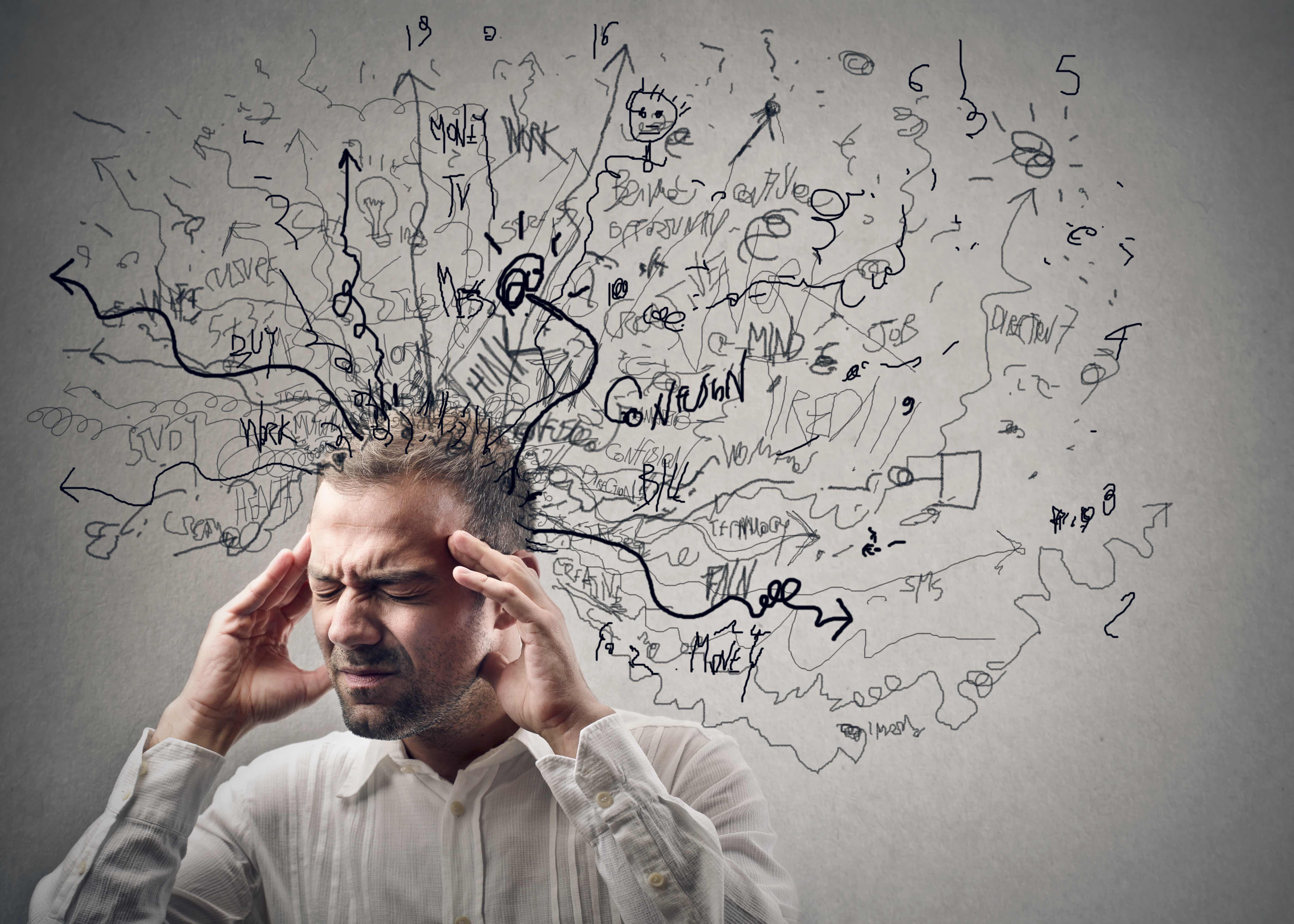
【富裕層だけの話じゃない】相続税で破産?世界の常識と日本のヤバい現実を徹底解説!
はじめに:相続税は、もはや他人事ではない
「相続税なんて、お金持ちだけの話でしょ?」——そう思っていませんか?実は、その考えはもう古いかもしれません。現代の日本において、富の移転に対する課税、つまり「相続税」は、社会の公平性や経済の活気に深く関わる、私たち全員にとって重要なテーマとなっています。
この記事では、世界の国々と比較しながら、日本の相続税が置かれている現状をわかりやすく解説します。特に、日本の中小企業を悩ませる「事業承継」の問題や、相続税が原因で資産が海外に流出してしまうリスクにも切り込みます。
相続税を廃止した国は、一体どんな未来を選んだのでしょうか?その成功と失敗から、私たちが学ぶべきことはたくさんあります。この記事を読めば、日本の相続税が抱える課題と、これから私たちがどう向き合っていくべきかのヒントが見つかるはずです。あなたの、そしてあなたの大切な家族の未来のために、ぜひ最後までお付き合いください。
第1章【世界との比較】日本の相続税は本当に「高い」のか?
課税の仕組み:2つの基本モデル
まず、相続税の基本的な仕組みには、世界的に見て大きく2つのタイプがあります。
- 遺産取得課税方式:相続人一人ひとりが「取得した財産」に対して課税される方式です。誰がどれだけもらったかによって税額が変わります。日本やフランス、ドイツがこのタイプです。
- 遺産課税方式:亡くなった人が「遺した財産全体」に対してまず課税され、税金を支払った残りが相続人に分配される方式です。アメリカやイギリスが採用しています。
このどちらを選ぶかで、税の性格が大きく変わってきます。
主要5カ国の制度を徹底比較!
表面的な税率だけでなく、「基礎控除額(ここまでなら税金がかからない、という非課税枠)」が実質的な負担を決めます。下の表で、その違いを見てみましょう。
| 国 | 課税方式 | 最高税率 | 基礎控除額(USD換算概算) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 遺産取得課税 | 55% | 約$240,000(相続人1人) | 最高税率は高いが、それ以上に基礎控除額が極端に低い。 |
| 米国 | 遺産課税 | 40% | 約$13,990,000 | 超高額な控除額により、課税対象はごく一部の富裕層のみ。 |
| 英国 | 遺産課税 | 40% | 約$410,000 | 配偶者への相続は非課税。夫婦単位で見ると非課税枠が拡大。 |
| フランス | 遺産取得課税 | 45% | 約$108,000(子へ) | 配偶者間は非課税。15年以内の生前贈与も加算される。 |
| ドイツ | 遺産取得課税 | 30% | 約$540,000(配偶者へ) | 親族関係が遠いほど税負担が重くなる設計が徹底されている。 |
この表からわかるのは、日本の相続税が「重い」と言われる本当の理由です。それは、世界トップクラスの最高税率(55%)と、アメリカなどと比べて著しく低い基礎控除額の組み合わせにあります。このため、日本では都市部に不動産を持つ中間層までもが課税対象となりやすい、という構造的な問題を抱えているのです。
国の財源として、相続税はどれくらい重要?
相続税が国の税収全体に占める割合を見てみると、日本の特殊な立ち位置がさらに明確になります。
| 国 | 相続・贈与税収の対総税収比 |
|---|---|
| 韓国 | 1.59% |
| フランス | 1.4%台 |
| 日本 | 1.33% |
| ドイツ | 0.5% |
| 英国 | 0.7%台 |
| 米国 | 0.5%台 |
| OECD平均 | 0.36% |
驚くべきことに、日本の相続税収の割合はOECD平均の3倍以上に達しており、G7諸国の中でも非常に高い水準です。これは、日本にとって相続税が単なる「富の再分配」のための象徴的な税金ではなく、社会保障などを支える現実的な財源として機能していることを意味します。安易に「相続税をなくせばいい」とは言えない、重い現実がここにあるのです。
第2章 日本の相続税が抱えるジレンマ
歴史を振り返る:なぜ今の形になったのか?
日本の相続税は、時代に翻弄されながら姿を変えてきました。
- 導入期(1905年):日露戦争の戦費調達という財源確保が目的でした。
- 転換期(1950年):戦後のシャウプ勧告により、富の集中を防ぐため最高税率90%という強烈な累進課税が導入され、「富の再分配」という役割が明確になりました。
- 緩和期(バブル期):地価高騰で中間層まで課税対象になるのを防ぐため、基礎控除額が大幅に引き上げられました。
- 強化期(2015年〜):財政難と格差是正のため、基礎控除額が4割も削減され、最高税率も55%に引き上げられました。これにより、再び多くの人が課税対象となる時代に逆戻りしたのです。
日本の格差のリアル:データで見る富の行方
相続税の議論の根底には、常に「格差」の問題があります。では、日本の格差は実際にどのようになっているのでしょうか?データを見てみましょう。
所得格差の動向:ジニ係数
所得格差を測る代表的な指標に「ジニ係数」があります。0に近いほど格差が小さく、1に近いほど格差が大きいことを示します。
| 年 | 当初所得ジニ係数 | 再分配所得ジニ係数 |
|---|---|---|
| 1995年 (平成8年) | 0.441 | 0.361 |
| 2005年 (平成17年) | 0.526 | 0.387 |
| 2015年 (平成26年) | 0.570 | 0.376 |
| 2021年 (令和3年) | 0.570 | 0.381 |
出典:厚生労働省「所得再分配調査」より作成
この表からわかるのは、税金や社会保障を考慮する前の「当初所得」の格差は拡大傾向にあるということです。しかし、年金や医療費の補助、そして税金による調整を経た後の「再分配所得」の格差は、2000年代以降ほぼ横ばいで推移しています。これは、日本の社会保障や税制度が、格差の拡大を一定程度抑制する役割を果たしていることを示しています。
資産格差の動向:富のシェア
所得(フロー)の格差以上に深刻なのが、資産(ストック)の格差です。日本では、一部の富裕層にどれだけの富が集中しているのでしょうか?
| 年 | 上位10%の富のシェア | 上位1%の富のシェア |
|---|---|---|
| 1980年 | データなし | 9.3% |
| 1995年 | 49.9% | 16.3% |
| 2010年 | 54.8% | 20.5% |
| 2021年 | 57.5% | 23.8% |
出典:World Inequality Database (WID.world) より作成
このデータは、日本でも富の上位集中が着実に進んでいることを示しています。特に上位1%の富裕層が持つ富の割合は、この40年で2.5倍以上に増加しています。所得格差は再分配である程度抑えられていても、一度築かれた資産の格差は、相続を通じて次世代に引き継がれ、固定化されていく危険性をはらんでいるのです。ここに、相続税が「富の再分配」という役割を担う重要な意味があります。
目指すべき格差水準とは?
では、私たちはどの程度の格差水準を目指すべきなのでしょうか?完全な平等(ジニ係数0)は現実的ではありませんし、経済の活力を損なう可能性もあります。しかし、過度な格差は社会の分断を生み、機会の平等を奪います。
多くの専門家が指摘するのは、特定の数値目標よりも、「格差が固定化されず、誰もが努力次第で豊かになれる流動性の高い社会」を目指すことの重要性です。相続税は、まさにその「格差の固定化」にブレーキをかけるための重要な政策ツールです。目指すべきは、相続税を単に重くしたり軽くしたりするのではなく、経済活動を阻害せずに、富の再分配という本来の機能を効果的に果たせるような、賢明な制度設計と言えるでしょう。
相続税はなぜ必要?そのメリットとは
批判も多い相続税ですが、もちろん存在する理由があります。
- 富の再分配と格差の固定化防止:親の資産が多いだけで、子の世代のスタートラインが大きく変わってしまうのは不公平です。相続税は、こうした「富の世襲」を和らげ、誰もがチャンスを掴める社会を目指すための重要なツールです。
- 社会保障の財源確保:少子高齢化が進む日本にとって、相続税は年金や医療、介護などを支える貴重な財源となっています。
見過ごせないデメリット:経済と社会への悪影響
しかし、そのメリットの裏で、深刻なデメリットも生まれています。
1. 「二重課税」という根強い不公平感
「所得税を払った残りの貯金に、死んだ後また税金がかかるのはおかしい!」という「二重課税」論争は、昔から絶えません。法的には「課税のタイミングと対象が違う」とされていますが、国民感情との間には大きな溝があります。最近では、生命保険金を年金形式で受け取るケースで、最高裁が「二重課税にあたる」と判断した事例もあり、この問題はさらに複雑化しています。
2. 中小企業の存続を脅かす「事業承継」問題
これが日本の相続税がもたらす最も深刻な経済的ダメージと言えるでしょう。中小企業の経営者の資産は、現金化しにくい自社の株式がほとんどです。経営者が亡くなると、後継者はこの株に対して高額な相続税を現金で支払わなければなりません。
納税資金がなければ、会社から無理やり資金を引き出したり、最悪の場合は会社や事業そのものを売却せざるを得なくなります。日本の技術や雇用を支える中小企業が、税金が原因で廃業に追い込まれるのは、国にとって大きな損失です。
もちろん、「事業承継税制」という納税を猶予・免除する制度はありますが、要件が非常に複雑で厳しく、使い勝手が悪いため、利用が進んでいないのが現状です。この問題についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの関連記事も参考にしてください。
3. 富裕層と資本の「海外流出」
高い相続税を嫌って、資産をシンガポールやオーストラリアといった相続税のない国に移す富裕層が増えています。これは、日本の税収が減るだけでなく、国内の投資や消費が冷え込む原因にもなりかねません。
国税庁も「国外財産調書制度」などで対策を講じていますが、根本的な解決には至っていません。2023年には、報告された国外財産の総額が6兆4,897億円に達しており、資産の国際分散が大規模に進んでいる実態が浮き彫りになっています。
第3章 相続税を「廃止」した国々のその後
近年、経済成長や事業承継の円滑化などを目的に、相続税を廃止する国が増えています。しかし、その結果はどうだったのでしょうか?代表的な国の事例を見てみましょう。
ケース1:カナダ - 相続税の代わりに導入された「死のキャピタルゲイン税」
カナダは1971年に相続税を廃止しましたが、課税を完全になくしたわけではありませんでした。代わりに導入したのが、「みなし譲渡キャピタルゲイン税」というユニークな制度です。
これは、人が亡くなった瞬間に、その人が持っていた資産(不動産や株など)を時価で売却したと「みなし」、購入時からの値上がり益(キャピタルゲイン)に対して所得税を課すというものです。理論的には非常にスマートですが、ここにも大きな落とし穴がありました。
それは、納税資金の問題です。実際に資産を売却して現金を得るわけではないのに、税金だけが発生するため、特にファミリービジネスの承継において、日本と同じように深刻な問題を引き起こしています。結局、納税資金を確保するために生命保険を活用するなどの対策が必須となっており、問題の本質は変わっていないのです。
ケース2:スウェーデン - 平等国家が格差拡大へ?
高福祉国家として知られるスウェーデンは、2004年に相続税を廃止しました。主な理由は、事業承継の妨げになっていたことや、富裕層は節税できるのに中間層の負担が重いという不公平感でした。
しかし、廃止後に何が起こったのでしょうか?下の表は、格差を示す指標の推移です。
| 年 | ジニ係数(所得格差) | 上位1%の富のシェア | 上位10%の富のシェア |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0.252 | 20.3% | 57.6% |
| 2004(廃止年) | 0.250 | 21.0% | 58.7% |
| 2021 | 0.298 | 28.6% | 74.4% |
データが示すように、相続税廃止後、スウェーデンの資産格差は一貫して拡大しています。もちろん、相続税廃止だけが原因ではありませんが、富の集中にブレーキをかける仕組みを失ったことが、格差拡大を加速させた一因であることは間違いないでしょう。かつて世界で最も平等な国の一つとされたスウェーデンは、今やOECD諸国の中で最も速いペースで格差が拡大している国の一つとなっています。
ケース3:オーストラリア - 40年後の富の集中
オーストラリアは1979年という早い段階で相続税を廃止しました。その長期的な影響を見てみましょう。
相続税がなくなってから40年以上が経過した現在、オーストラリアの資産格差は著しく拡大しています。あるデータによれば、上位1%の富裕層が持つ富の割合は、1980年の9.9%から2021年には23.8%へと2倍以上に増加しています。
オーストラリアの経験は、相続税の廃止が、社会の富の分配構造に長期的かつ重大な影響を及ぼす可能性があることを強く示唆しています。
ケース4:ポルトガル - 相続税廃止と「印紙税」という選択
ヨーロッパの国々の中でも、ポルトガルは2003年に相続税を廃止するという早期の決断を下しました。その背景には、他の国々と同様に、富裕層の海外流出を防ぎ、逆に国外からの投資を呼び込みたいという経済的な狙いがありました。
しかし、ポルトガルが選んだ道は、完全な無税化ではありませんでした。相続税の代わりに導入されたのが「印紙税(Imposto do Selo)」です。この制度が非常にユニークなのは、その課税対象の定め方です。
| 相続人との関係 | 税率 | 対象資産 |
|---|---|---|
| 配偶者、子・孫、親・祖父母(直系親族) | 0%(非課税) | - |
| 兄弟、いとこ、友人など上記以外 | 10% | ポルトガル国内の資産のみ |
つまり、ポルトガルの制度は、家族内での資産承継は完全に非課税とし、それ以外への富の移転にのみ課税するという、非常に割り切った設計になっています。これは、富の再分配というよりも、「家族の財産を守り、円滑な世代交代を促す」という目的を最優先した結果と言えるでしょう。
廃止後の経済と格差への影響
この税制は、海外の富裕層にとって非常に魅力的であり、特に「ゴールデンビザ」制度と組み合わせることで、ポルトガルへの移住や投資を促進する大きな要因となりました。
では、格差への影響はどうだったのでしょうか?驚くべきことに、スウェーデンやオーストラリアとは対照的に、ポルトガルの所得格差を示すジニ係数は、相続税廃止後に拡大するどころか、むしろ減少傾向を示しています。
これは、相続税廃止が直接格差を縮小させたわけではなく、同時期に進行したEU加盟後の経済成長や、最低賃金の引き上げといった他の社会経済政策が、格差拡大を抑制する方向に強く作用したためと考えられます。
ポルトガルの事例は、相続税を廃止しても必ずしも格差が拡大するわけではないこと、そして「直系親族への承継を優遇する」という形で課税を残す、日本にとっても示唆に富んだ「第三の道」を示しています。
結論:日本の相続税、これからどうなる?私たちが取るべき道とは
世界の事例を見てくると、日本の相続税が抱える問題の根深さがわかります。では、私たちはこれからどうすればいいのでしょうか?
スウェーデンやオーストラリアの例が示すように、単純な「廃止」は、格差の拡大という新たな、そしてより深刻な問題を生むリスクがあります。また、カナダの例は、課税の形を変えても、事業承継における納税資金の問題は解決しないことを教えてくれます。
日本が進むべき道は、単純な廃止ではなく、制度の「賢い再設計」です。その核心は、「生産的な資産(事業用資産)」と「それ以外の富」を税制上、明確に区別することにあります。
- 事業承継はもっとスムーズに:ドイツやフランスのように、一定の条件を満たせば事業用の資産にかかる相続税を大幅に軽減・免除する制度へと、現行の複雑な事業承継税制を抜本的に改革すべきです。これにより、企業の存続と雇用の維持を図ります。事業承継やM&Aを検討している経営者の方は、専門家への相談をおすすめします。
- 富の再分配機能は維持する:事業承継への配慮を徹底する一方で、それ以外の純粋な富の移転に対しては、格差が固定化しないよう、適切に課税を続ける必要があります。
- 寄付文化の促進:相続財産を税金として国に納めるだけでなく、認定NPO法人などに寄付することで非課税になる制度をもっと活用しやすくし、個人の意思で社会に貢献できる道を広げることも重要です。
日本の相続税は今、「公平性」「経済成長」「財政の健全化」という3つの難しい目標をどう両立させるかという、大きな岐路に立たされています。これは、私たち一人ひとりが自分の問題として考え、議論していくべきテーマなのです。




