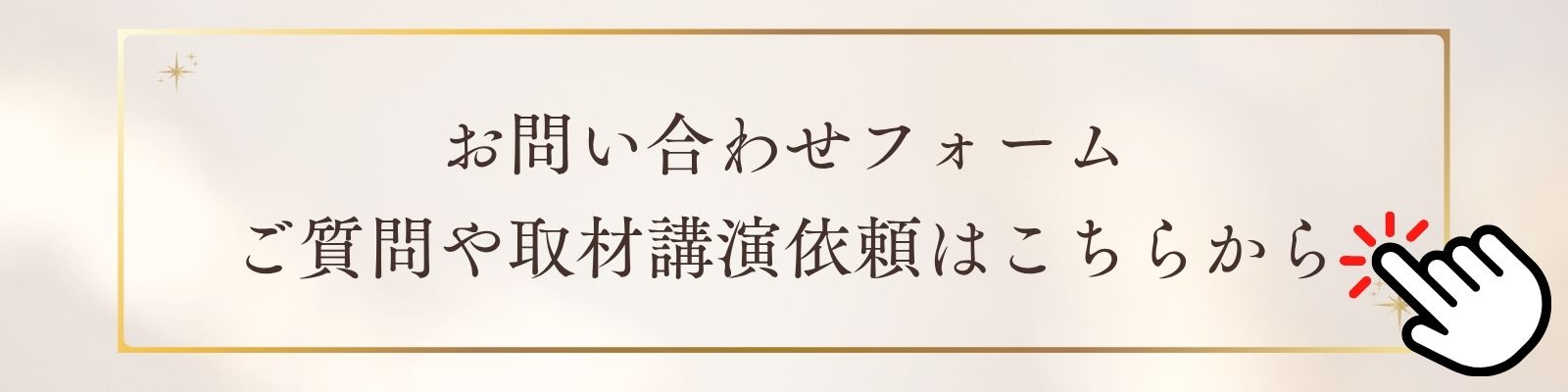記事公開日
<Part3> 能力が高くても成果が出ない構造とその構造的解決策

第一部→ https://hr.my-sol.net/media/useful/a160
第二部→ https://hr.my-sol.net/media/useful/a161
結論:構造的解決策としての「動力マネジメント」
これまで見てきた根深い構造問題を解決するためには、精神論や個人の努力に頼るのではなく、マネジメントのあり方そのものを根本からアップデートする必要があります。私はその解決策を、個人の内なる力を組織の力に転換する「動力マネジメント」と呼んでいます。これは単なる概念ではなく、具体的な3つの仕組みの改革です。
解決策①:長期視点を育む「仕組み」の導入
短期的な成果主義から脱却し、経営者が腰を据えて長期的な視点で意思決定できる環境を制度的に整えることが不可欠です。例えば、経営者の報酬体系において、単年度の利益に連動するボーナスの比率を下げ、数年単位で受け取れるストックオプションや、5年後・10年後の企業価値向上に連動するインセンティブの比率を高めるのです。これにより、経営者は株主の短期的な要求から自らを守り、未来のための大胆な投資や改革に踏み切るインセンティブを持つことができます。
解決策②:マネージャーを「伴走者」へと役割転換する
社員一人ひとりの「動力」を経営の根幹に据える仕組みを構築します。その鍵を握るのがマネージャーの役割転換です。業務の進捗を管理し、指示を出す「管理者」から、メンバーの人生観や価値観に寄り添い、その「動力」と会社の目標を結びつける「伴走者(パートナー)」へと変わるのです。具体的には、定期的な1on1ミーティングにおいて、「今、何に一番情熱を感じるか?」「もし会社のリソースを自由に使えたら何がしたいか?」といった問いを通じて、個人の内なる声を引き出し、それを実現できるような仕事の機会を一緒に探していくことが求められます。
解決策③:組織の「共通言語」を創造し、浸透させる
そして最も重要かつ即効性のある解決策が、「言葉の定義」を社内で徹底的に統一し、組織の「共通言語」を創造することです。これは単なる言葉遊びではありません。「問題とは何か」「課題とは何か」「戦略とは何か」といった基本用語の定義を全社で合意し、それをまとめた「思考のプレイブック」を作成・共有するのです。これにより、社員は同じ物差しで考え、話せるようになります。これは思考の解像度を高め、誤解や手戻りをなくし、組織全体の意思決定の精度とスピードを飛躍的に向上させるための、知的生産性のためのインフラ整備なのです。
繰り返しますが、日本人の能力は、今も昔も世界に誇れるものです。私たちに足りないのは個人の能力ではなく、その能力を最大限に引き出し、一つの大きな力として結集するための「構造」、すなわちマネジメントの仕組みです。過去の成功体験から生まれた古い思い込みという名の「呪縛」を解き放ち、個の「動力」を組織の力へと転換する新しいマネジメントへと、今こそ舵を切るべきです。その先にこそ、日本の産業が再び世界のメインステージに返り咲く道があると信じています。