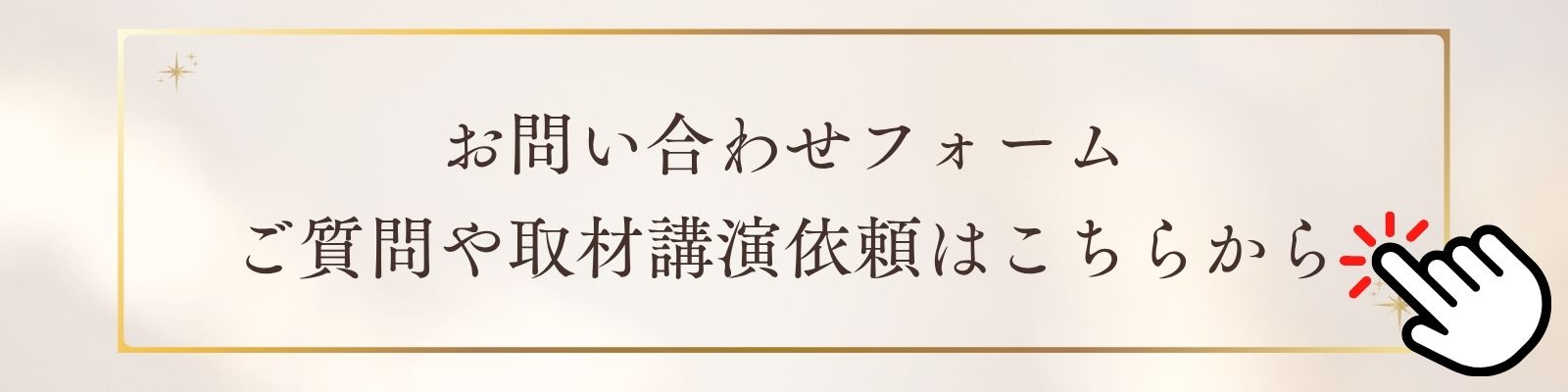記事公開日
② 失われた栄光。なぜ日本の半導体は勝てなくなったのか? パート2

【第二部】成果を阻む3つの呪縛。あなたの組織は大丈夫か?
構造の正体:日本のマネジメントが持つ「3つの思い込み」
多くの日本企業、特に歴史ある大企業のマネジメント層は、長年の成功体験の中で形成された「常識」に基づいて行動しています。しかし、その良かれと思って実践している行動が、変化の激しい現代においては、結果的に組織のポテンシャルを蝕んでいるという事実に気づいていません。その根底には、今や成長の足かせとなっている共通の価値観が存在します。それが「日本のマネジメントが持っている3つの思い込み」という名の呪縛です。
思い込み①:任期中に成果を出す(短期志向の罠)
日本の大企業の多くは、内部昇進で社長に就任する、いわゆる「サラリーマン経営者」によって運営されています。そして、その任期は1990年代以降、短期化の一途をたどってきました。短い任期の中で株主や金融機関への説明責任を果たし、自らの評価を確立するためには、どうしても在任期間中に目に見える成果、特に短期的な利益を最大化することが至上命題となってしまいます。
しかし、半導体産業は、一つの工場に数兆円規模の投資を必要とし、基礎研究から製品化、そして市場での成功までに数年から十年単位の歳月を要する、極めて長期的な視点が不可欠なビジネスです。短期的な利益確保のために、未来の屋台骨となるはずの長期的な研究開発投資を削減したり、リスクは大きいがリターンも大きい次世代技術への挑戦を先送りにしたりする。このような意思決定は、企業の未来の競争力を確実に、そして静かに削いでいくのです。果樹園の経営に例えるなら、今ある果実を収穫することに夢中で、新しい苗木を植え、育てることを怠っているようなものです。
思い込み②:会社のビジョン・ミッションから始める(トップダウンの限界)
多くの企業では、経営陣が練り上げた崇高なビジョンやミッションを、研修や社内報を通じてトップダウンで現場に浸透させようと多大な努力を払っています。しかし、その美しく、論理的な言葉が社員の心を本当に動かし、自発的で熱量の高い行動につながることは稀です。それは、「やらされ感」を生み出し、真のコミットメントには繋がりにくいからです。
なぜなら、イノベーションやブレークスルーの真の源泉は、会社の計画書の中にはなく、個人の内側からマグマのように湧き上がる「動力」にあるからです。この「動力」とは、個人の人生観や価値観、「こうありたい」「これを成し遂げたい」という強い願いであり、良い意味での「わがまま」と言い換えることもできます。歴史を振り返れば、ソニーのウォークマンや3Mのポストイットなど、世界を変えた製品の多くは、会社の緻密な計画や指示からではなく、担当者の「こんなものがあったら面白い」という個人の情熱や遊び心から生まれています。
思い込み③:話せば分かる(コミュニケーションの幻想)
私たちは、「同じ日本語を話しているのだから、互いに理解し合えるはずだ」と無意識に信じています。しかし、ビジネスの現場では、基本的な用語の「言葉の定義」が驚くほど統一されておらず、これが組織に「見えざるコスト」を発生させ、生産性を著しく下げています。
例えば、あなたの組織では、「問題」と「課題」はどう違うでしょうか。「問題」とは「あるべき姿と現状のギャップ」であり、「課題」とは「そのギャップを埋めるための具体的な行動計画」です。この区別が曖昧だと、「問題は何か?」と聞いているのに延々と解決策(課題)が語られたり、逆に課題を議論すべき場面で問題点の指摘に終始したりと、議論が全く噛み合いません。他にも「目的と目標」「戦略と戦術」など、定義が曖昧なまま使われている言葉は無数に存在します。