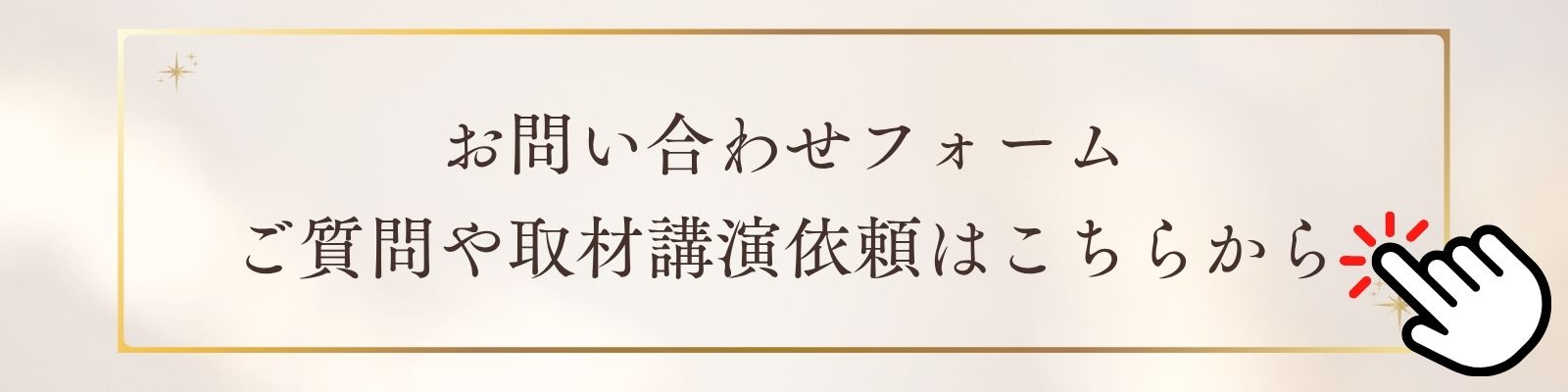記事公開日
① 失われた栄光。なぜ日本の半導体は勝てなくなったのか? パート1

【第一部】失われた栄光。なぜ日本の半導体は勝てなくなったのか?
はじめに:高い能力と、失われた成果のパラドックス
1990年、世界の半導体売上高ランキングのトップ10に、NEC、東芝、日立製作所をはじめとする日本企業が実に6社もランクインし、世界市場を文字通り席巻していました。当時の日本の半導体産業は、その圧倒的な品質管理と製造技術を武器に、他国の追随を許さない絶対的な王者として世界に君臨していたのです。
しかし、それから約30年の時が流れた現在、その光景は見る影もありません。ランキング上位は、ファブレス(工場を持たない設計専門企業)のNVIDIAや、巨大な投資力で市場をリードする韓国のSamsungなどに独占され、日本企業の名前を見つけること自体が困難な状況です。この間に、一体何が起きたのでしょうか。日本の技術者や従業員の能力が、30年で急激に低下してしまったのでしょうか。

その答えは明確に「否」です。経済協力開発機構(OECD)が実施した国際成人力調査(PIAAC)を詳しく見れば、日本人の「読解力(複雑な文章を理解し評価する力)」や「数的思考力(数学的な情報を応用する力)」といった、ビジネスの根幹をなす基礎能力は、今なお世界トップクラスを維持していることが分かります。現場で働く一人ひとりのポテンシャル、問題解決能力は、決して衰えていないのです。

個々の能力は高い。しかし、組織として、産業として成果が出ない。この深刻で根深いパラドックスの根源は、個人の資質の問題ではなく、私たちを覆い、その能力の発揮を阻害している「構造」そのものにあります。それは、まるで高性能なエンジンを積んでいるのに、ブレーキがかかったままアクセルを踏んでいるような状態です。この連載記事では、この「見えざるブレーキ」の正体である構造的問題を3つのパートに分けて解き明かし、日本が再び輝くための構造的な解決策を提示していきます。