記事公開日
最終更新日
計画された偶発性理論と組織への応用
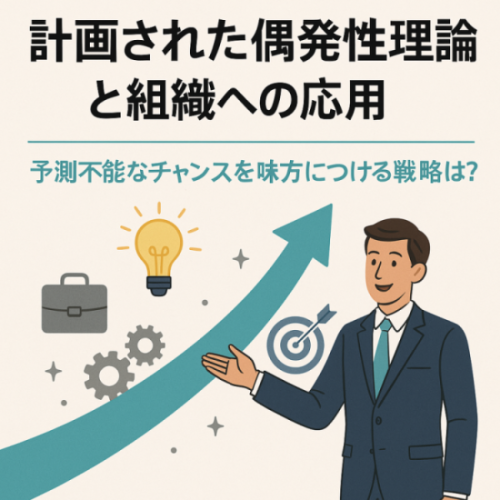
計画された偶発性理論 ―予測不能なチャンスを味方につける戦略とは?―
計画された偶発性理論(Planned Happenstance Theory)は、「キャリアや組織の成功は、予測できない偶然の出来事をどう活かすかにかかっている」という考え方に基づいています。個人や組織が「偶然の出会い」や「予想外の変化」をチャンスに変えるには、特定のスキルや姿勢が必要です。この理論は、キャリア形成だけでなく、イノベーションや人材開発、組織変革にも応用可能です。

計画された偶発性理論とは?
計画された偶発性理論(Planned Happenstance Theory)は、1999年にアメリカの心理学者ジョン・D・クランボルツによって提唱されました。この理論は、偶然を「予測不能なリスク」ではなく、「戦略的に活用すべき機会」として捉え直す点が特徴です。
チャンスを生かす5つの「態度」とは?
クランボルツは、偶然をチャンスに変えるために、以下の5つの態度が重要であるとしています。
- 好奇心(Curiosity):常に新しい学びの機会を探求する
- 持続性(Persistence):失敗しても諦めず、努力し続ける
- 柔軟性(Flexibility):こだわりを捨て、考えや行動を変化させる
- 楽観性(Optimism):新しい機会は必ず実現できると信じる
- リスクテイク(Risk Taking):結果が不確実でも、恐れず行動する
これらの態度は、予期しない出来事や情報を前向きに受け入れ、行動に移すための基盤となります。
偶然を「仕組み」に変える組織への応用
この理論は、個人のキャリアだけでなく、組織全体にも応用できます。
人材育成における応用
社員の多様な経験や挑戦を促進する制度(ジョブローテーション、副業制度、自己申告型異動など)は、偶発的な学びや発見の機会を増やします。こうした越境学習は、個人の成長と組織の活性化に繋がります。
イノベーション戦略として
他部署や社外との偶然の接点が新しい価値を生むきっかけになります。フリーアドレスや社内SNS、異業種交流会への参加支援など、意図的に「セレンディピティ(偶然の幸運な出会い)」を誘発する仕掛けが有効です。また、挑戦を許容する「心理的安全性」の高い企業文化も、偶然を活かす重要な要素です。
偶然をチャンスに変えた実践事例
【Google】20%ルールとGmailの誕生
Googleでは、社員が勤務時間の20%を自由なプロジェクトに使える制度を導入。この「余白」が、GmailやGoogleニュースなどの革新的なサービスを生み出しました。まさに、「計画されていない挑戦」から生まれた成果です。
【3M】ポスト・イットの誕生
3Mの研究者が失敗から偶然発見した「よくつかない弱い接着剤」が、別の社員の「楽譜に挟むしおりが落ちる」という悩みと結びつき、「ポスト・イット」として商品化されました。3Mには失敗や試行錯誤を推奨する文化があり、偶然の発見を見逃さず形にする体制が整っています。
【パナソニック】社内提案制度と“現場力”の活用
パナソニックでは、現場からの提案を奨励する文化があり、ちょっとした現場の「気づき」や偶発的な発想が商品改善や新規企画につながっています。この「現場の偶然」を活かすには、上司や組織全体の受容性とスピード感も欠かせません。
まとめ
計画された偶発性理論は、単に偶然を待つのではなく、偶然が起こりやすい環境を「意図的に設計」し、起きた偶然をチャンスに変えるための戦略です。
これからの組織づくりにおいては、緻密な戦略計画と並行して「柔軟な余白」と「偶然を受け入れる文化」を持つことが、持続的な成長のカギとなります。




