記事公開日
最終更新日
リフレーミングで組織を変える
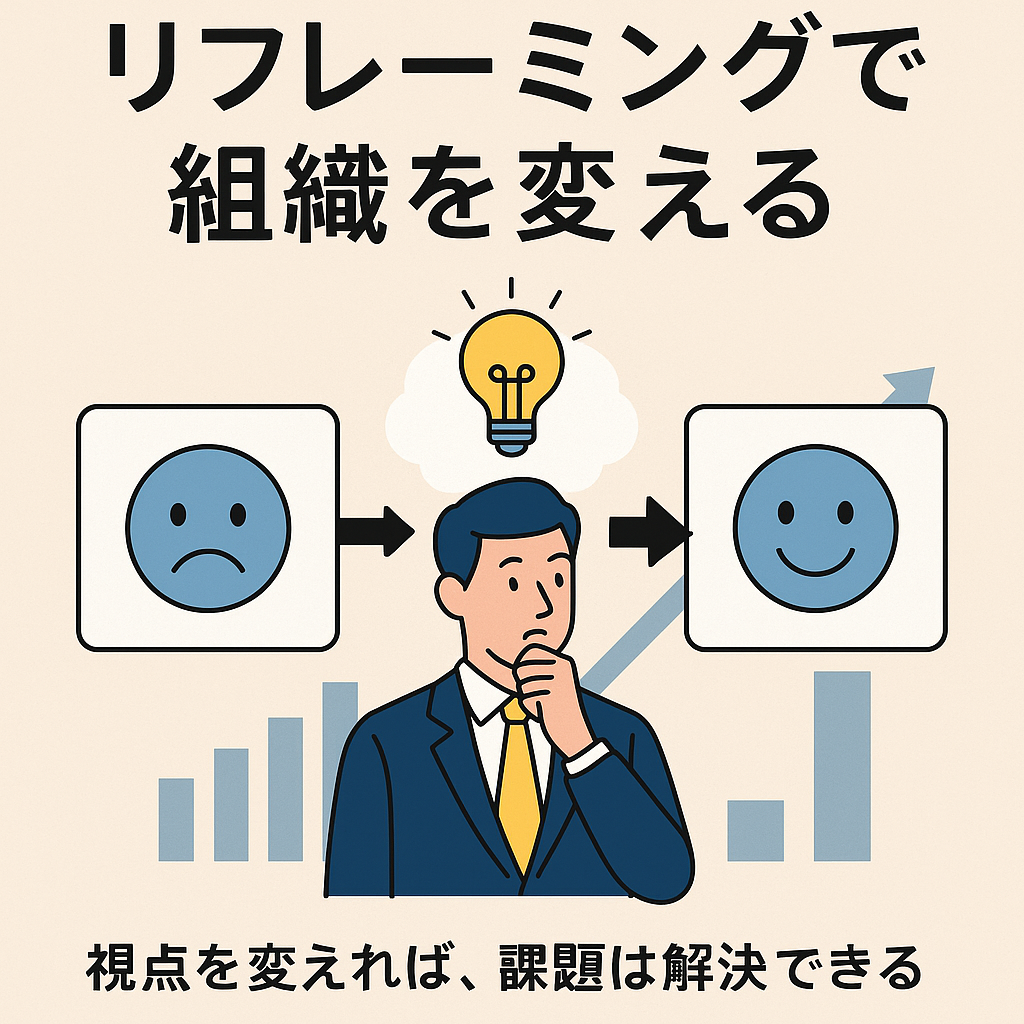
リフレーミングとは?組織と人の可能性を引き出すマネジメント術
リフレーミング(Reframing)とは、出来事や課題の「見方=フレーム」を意図的に変え、意味づけを再構築する思考技法です。組織マネジメントにおいては、対立・停滞・人材育成の行き詰まりなどの問題を、新たな視点で捉え直すことで、解決の糸口を見出す強力なアプローチになります。現代の複雑な組織環境では、「正解を探す」のではなく「意味を再構築する」能力が、マネージャーに求められています。

リフレーミングとは? ─心理学にルーツを持つ思考法
リフレーミングは元々、心理学(とくに認知行動療法)で用いられる技法です。人は同じ出来事でも、「どのフレーム(枠組み)」で見るかによって、全く異なる感情・判断・行動をとる傾向があります。
例1:「部下が質問してこない」
- 元の見方:「やる気がない」
- リフレーミング後:「自立して動こうとしているのかも」
- 対応の変化:「観察し、フォローのタイミングを調整しよう」
例2:「失敗が続いているプロジェクト」
- 元の見方:「管理不全だ」
- リフレーミング後:「今は試行錯誤を重ねる重要なフェーズかもしれない」
- 対応の変化:「学びの共有を重視し、支援体制を構築する」
マネジメント論におけるリフレーミングの意義
現代のマネジメントにおいて、リフレーミングは単なる認知の工夫にとどまらず、組織開発やリーダーシップ理論における中核的なスキルとして位置づけられています。なぜなら、組織で起きる問題や停滞の多くは、「状況そのもの」よりも「その捉え方」によって悪化・長期化するからです。
組織における「意味のズレ」が生産性を下げる
例えば、あるプロジェクトの遅延について、経営側のフレームが「現場の責任」、現場側のフレームが「無理な納期設定の結果」というように食い違うと、対話がすれ違い、対立が深まります。リフレーミングとは、こうした「見方のズレ」を発見し、“再定義”することで対話の前提を整える技術とも言えます。
マネジメントにおける3つのリフレーミング視点
- 問題を「問い」に変える力
「なぜできていないのか?」ではなく、「どんな仕組みなら可能になるか?」と問いを変えることで、責任追及から創造的な対話へ転換できます。 - 失敗を「学び」と捉える視点
ミスを責めるのではなく、「何を学べたか」「何を改善できるか」というフレームを持つことで、組織の心理的安全性が高まり、挑戦が増えていきます。 - 「個人の行動」を「関係性の結果」と見る視点
問題行動を個人の資質のせいにするのではなく、その背景にある組織構造・コミュニケーション・文化に目を向けることで、再発防止と風土改革が可能になります。
リーダーに求められるのは「多視点」の統合力
現代の組織では、多様な人材や価値観が共存しています。その中でリーダーに求められるのは、「どの視点が正しいか」を決めつける力ではなく、異なるフレーム同士を“つなぎ直す”調整力と創造性です。つまりリフレーミングとは、単なる問題解決ではなく、「意味のデザイン」を担うマネジメント行為なのです。
リフレーミングが効果を発揮するマネジメントシーン
- 部下育成:「注意しても改善されない」 → 「その指摘は本人の価値観とズレているのでは?」と見方を変え、行動の背景にある価値観に焦点を当てる。
- 組織内対立の調整:「意見が対立してまとまらない」 → 「両者の前提が違っているだけでは?」と捉え、フレームを揃える対話の場を設ける。
- 働きがいの再設計:「ルーティン作業でモチベーションが低い」 → 「安定稼働を支える重要な役割では?」と仕事の意味を再定義し、共有する。
実際の企業の応用事例
■ トヨタの「なぜなぜ分析」
問題が起きたときに「なぜ?」を5回繰り返して真因を探る手法は、問題を「再定義=リフレーミング」する技法そのもの。表面的な見方を超えて、本質的な改善が促されます。
■ スターバックスのクレーム対応
クレームを「問題」ではなく、「ブランド価値を高める絶好の接点」と見なす。これもリフレーミングの応用で、社員の対応姿勢や意欲に良い影響を与えています。
まとめ
視点を変えれば、組織は変わる。リフレーミングは「起きている事実」を変えるのではなく、「その捉え方=意味づけ」を変える手法です。管理職やリーダーがこれを活用すれば、人の可能性や組織の潜在力を引き出す新しいマネジメントが実現します。
問題が見えたときこそ、「見方を変える」チャンスです。




