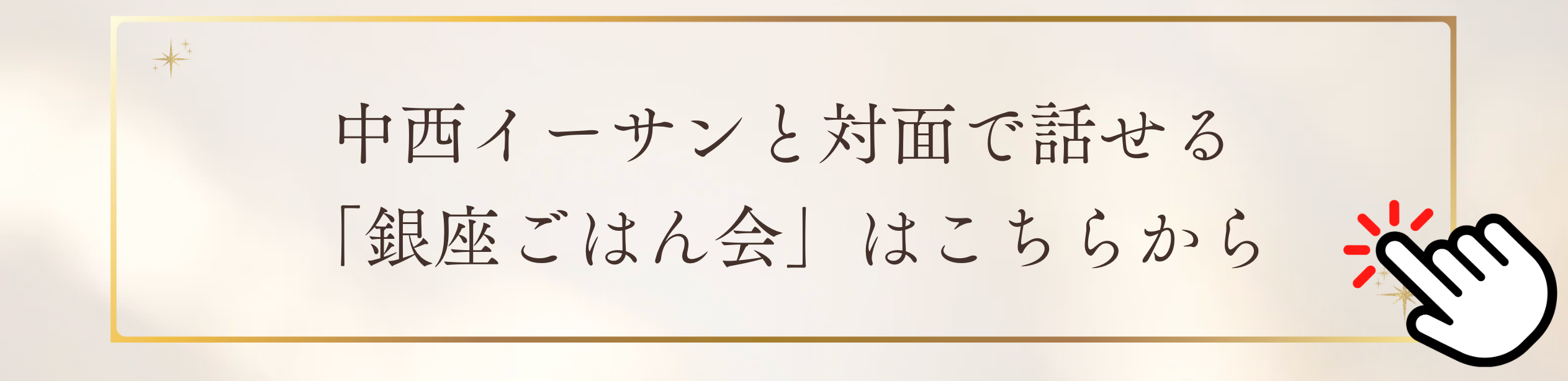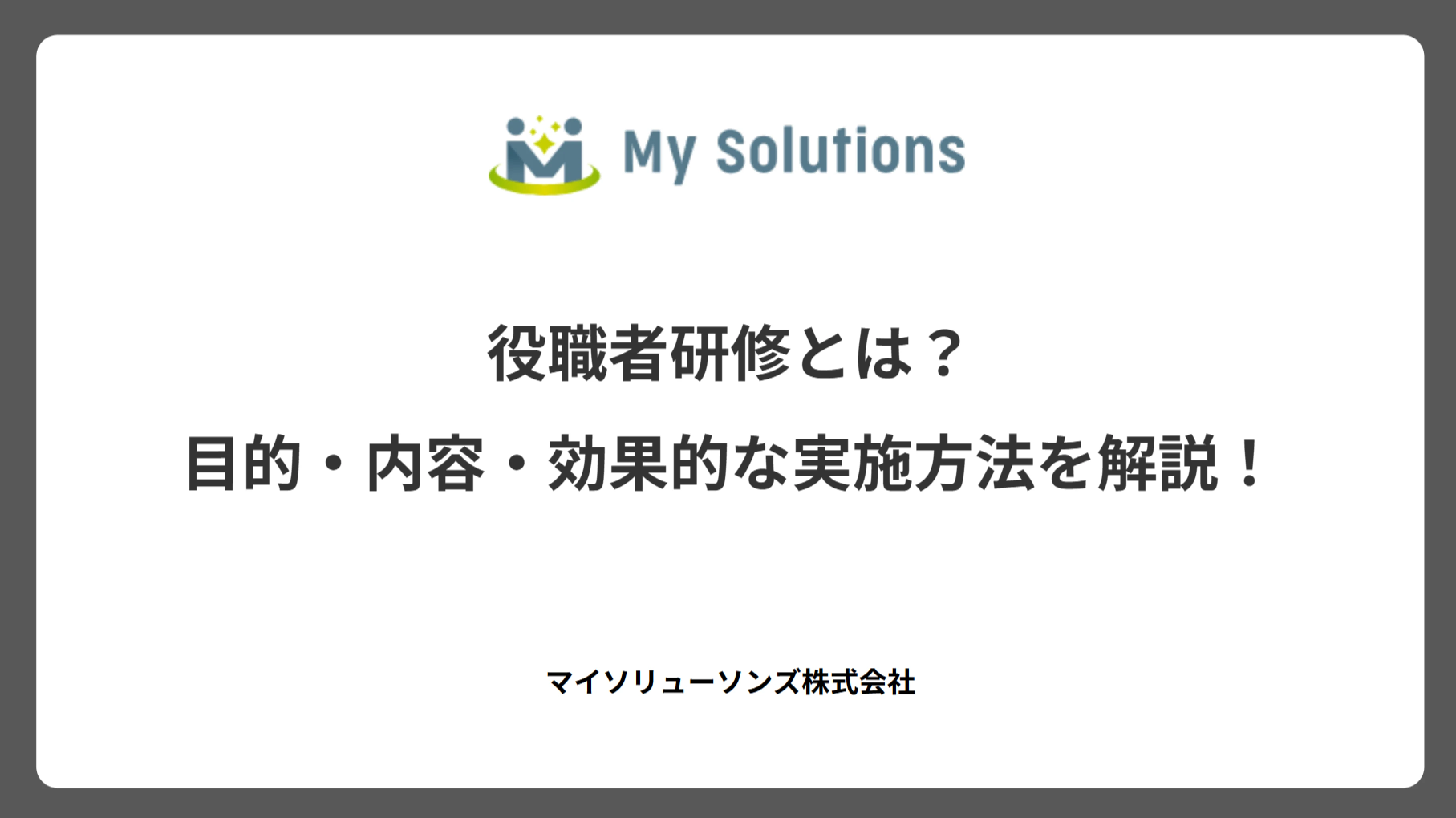「病院の経営って、一体どうなっているんだろう?」
普段、私たちが風邪やケガで病院にかかるとき、その裏側でどれほど複雑な経営課題が渦巻いているかは、なかなか想像しにくいものです。
日本の医療機関は今、少子高齢化、人材不足、そして「2024年医師の働き方改革」といった大きな波に直面しています。まるで、向かい風の中で進む船のように、さまざまな課題を乗り越えながら、かじ取りをしていかなければなりません。
今回は、そんな病院経営の「今」を深く掘り下げ、どんな課題があり、どうすれば未来を切り拓けるのか、5つの視点から考えていきます。
第1部:病院経営を悩ませる「4つの難問」
まずは、多くの病院が共通して抱える、深刻な4つの課題を見ていきましょう。
1. お金の悩み:なぜ収益が増えても利益が減るのか?
病院の経営を圧迫する最大の要因は、支出の増加です。特に、人件費は病院の経費の半分以上を占めており、医師や看護師の給与上昇が大きな負担となっています。
さらに、最近の物価高騰は病院経営に追い打ちをかけています。医薬品や医療材料だけでなく、電気・ガス代も急騰しており、2022年度には水道光熱費が前年比で38.8%も増えたというデータもあるほどです。
ところが、病院の収入源である「診療報酬」は、国が定める公共料金のようなもの。コストが上がっても、自由に料金を上げることができません。その結果、多くの病院で「増収減益」という不思議な現象が起きています。これは、収益は増えても、それ以上に経費が増えることで、手元に残る利益が減ってしまうという、まさに「もぐらたたき」のような状況なのです。
また、入院患者の減少も大きな問題です。2022年度の一般病床の利用率は69.0%にとどまっており、入院収益に依存する病院にとっては、経営悪化の直接的な原因となっています。
2. 人の悩み:なぜスタッフが足りない、辞めていくのか?
日本の医療現場は、慢性的な人手不足に悩まされています。特に地方では、給与や生活の利便性の差から、人材が都市部に集中する傾向があります。
この人員不足は、現職のスタッフに過度な負担をかけ、高い離職率を引き起こしています。日本看護協会の調査では、2023年度の正規雇用看護師の離職率は11.3%です。離職の背景には、精神的な負担、劣悪な労働環境、人間関係の悪化など、様々な要因が絡み合っています。
そして、2024年4月から始まった「医師の働き方改革」。これは医師の長時間労働を是正するための制度ですが、その効果はまだ道半ばです。規制後も、医師の60.3%、看護師の77.7%が労働時間の短縮を実感できておらず、「隠れ残業」が増えたと感じるスタッフも少なくありません。
人員不足という根本的な問題が解決されないままでは、業務負担が他の職種に転嫁されたり、サービスの質が低下したりするリスクも指摘されています。
3. 業務の悩み:なぜ仕事が非効率で、ミスが減らないのか?
多くの医療機関では、いまだに紙のカルテや手作業での事務処理が主流です。これでは、業務効率が上がらないのは当然のこと。紙のカルテは探すのに時間がかかり、手書きの文字が読めない、転記ミスが起きるなど、ヒューマンエラーのリスクを高めてしまいます。
非効率な業務は、患者さんの待ち時間増加にもつながります。予約システムがない、いつ診てもらえるか分からないといった状況は、患者さんの不満を増大させ、病院への信頼を損ないかねません。
医療安全は最優先の課題ですが、業務の非効率性は、スタッフの疲弊を招き、事故やヒヤリ・ハットの温床となりがちです。
4. 将来の悩み:2025年問題と病院の役割
2025年、日本の人口構造は大きく変わります。団塊の世代が75歳以上となり、国民の3人に1人が高齢者となる「2025年問題」が到来するのです。
医療需要が急増する一方で、医療を支える労働人口は減少します。この変化に対応するには、病気を「治す医療」だけでなく、生活を「支える医療」へと、病院の役割そのものを変える必要があります。
これからの病院は、地域全体で医療や介護を提供する「地域包括ケアシステム」の一員として、他の施設と連携していくことが不可欠です。人口減少が進む地域では、病床数を減らすといった「再編」も視野に入れ、地域のニーズに合わせた経営戦略を立てる必要があるのです。
第2部:未来を拓く「5つの視点」と解決策
では、これらの難問を乗り越え、持続可能な病院経営を実現するためには、どうすればいいのでしょうか。
1. 収益改善の鍵は「見える化」と「適正化」
まずは、自院のコスト構造を「見える化」することが第一歩です。
- 人件費の最適化:勤怠管理を徹底し、タスク・シフト/シェア(業務の分担)や、定型業務の外部委託も検討しましょう。非正規職員の雇用を増やすことも、人件費の抑制に効果的です。
- 経費の削減:医薬品や医療材料の仕入れ条件を見直したり、業者と価格交渉をしたりすることで、大きなコスト削減が期待できます。省エネ機器の導入も有効です。
- 収益の向上:病床の稼働率を上げるために、地域のニーズに合わせた「地域包括ケア病棟」などを増設するのも一つの手です。患者さんの満足度を高め、リピーターを増やすことも重要です。
2. スタッフが輝く「働きやすい環境」を創る
人材不足を解消するには、採用と定着の両面からアプローチが必要です。
- 業務負担の軽減:医師の業務を看護師や事務員など、他の職種に分担する「タスク・シフト/シェア」を推進しましょう。ただし、負担が一方に偏らないよう、適切な人員配置と研修が欠かせません。
- 柔軟な働き方:シフト制や短時間勤務など、多様な働き方を導入することは、過労を防ぎ、離職防止につながります。
- 心のケア:職員間のコミュニケーションを活発にし、感謝し合う文化を醸成することも、精神的な負担を減らし、心の健康を支える上で非常に大切です。
3. 「DX」で業務をスマートに
デジタル化(DX)の推進は、非効率な業務を解決する特効薬です。
- 電子カルテ:紙のカルテから電子カルテに移行すれば、情報の検索や共有がスムーズになり、手書き文字の判読ミスなども防げます。
- AIの活用:日本赤十字社や福岡和白病院、大阪国際がんセンターではAI問診ツールを導入し診察時間を短縮。広島赤十字・原爆病院や小松病院では画像診断AIで医師の診断をサポート。東北大学病院や京都大学医学部附属病院、恵寿総合病院では大規模言語モデル(LLM)で医療文書の作成時間を大幅に削減するなど、AI技術はすでに多くの病院で活用されています。
| ソリューション | 解決する課題 | 具体的な効果 |
|---|---|---|
| 電子カルテ | 業務効率、情報共有、医療安全 | リアルタイムの情報共有、手書き文字の判読ミス防止、医療事故の未然防止 |
| AI問診ツール | 業務効率、患者満足度 | 診察時間の短縮、カルテ記入の自動化、待ち時間の解消 |
| 画像診断AI | 医療安全、業務効率 | 胸部X線などからの病変検出支援、診断精度の向上、見落としリスクの低減 |
| LLM | 業務効率 | 医療文書の作成時間を最大47%削減、診療報酬算定作業の効率化 |
| 遠隔医療 | 患者満足度、地域連携 | 患者の通院負担軽減、在宅医療への対応、地域連携の強化 |
4. 医療の質と安全を「デザイン」する
医療安全管理は、患者さんの安全を守るだけでなく、病院の信頼性にも関わる重要な経営課題です。
- リスクマネジメント:事故やヒヤリ・ハットを未然に防ぐために、リスクの特定から分析、対策立案、評価までを継続的に行うことが大切です。
- 質改善(QI):医療の質を表す指標を数値化し、「見える化」することで、客観的に課題を把握し、継続的な改善につなげることができます。
5. 「地域」とともに歩む
これからの病院は、単独で生き残るのではなく、地域全体の中で自らの役割を再定義することが求められます。
- 地域包括ケアシステムへの貢献:在宅医療や介護サービスとの連携を強化し、患者さんの在宅復帰を支援する「橋渡し」役を担いましょう。
- 他施設との連携:特定の医療分野に専門特化し、他の病院や診療所と協力することで、地域全体で効率的かつ質の高い医療を提供できます。
おわりに
現代の医療機関が直面する課題は、互いに絡み合った複雑なものです。しかし、成功事例が示すように、データに基づいた経営、働きやすい環境づくり、そしてデジタル技術の活用を組み合わせることで、必ず乗り越えることができます。
これからの病院経営は、単なる「治療の場」にとどまらず、地域や社会と深く連携しながら、より良い未来をデザインしていく「創造的な営み」へと進化していくでしょう。病院経営改善、医療現場のDX化、人材育成や定着、リスクマネジメントに関する詳しい情報は、マイソリューションズのコラムでご覧いただけます。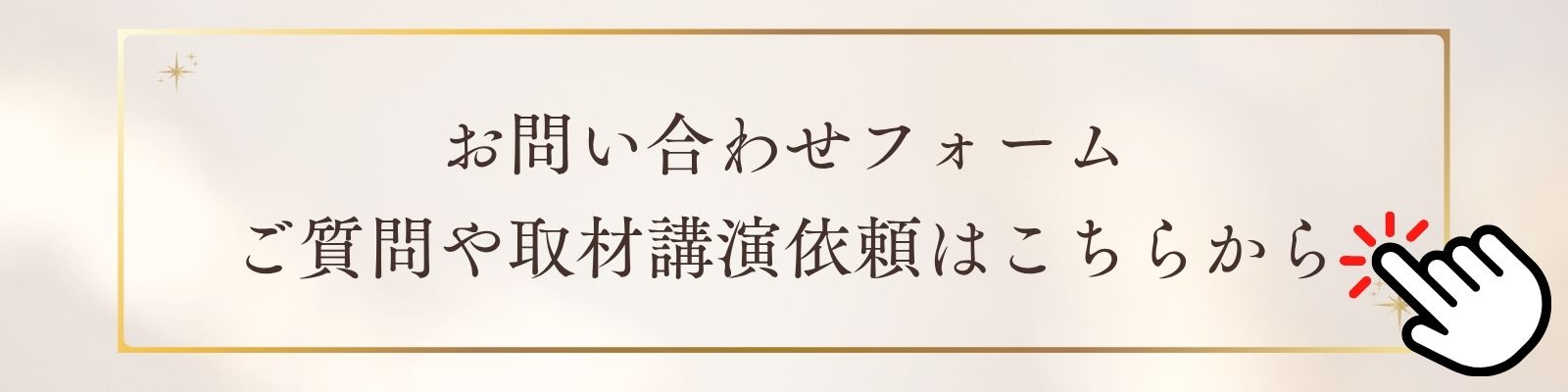
編集者: マイソリューションズ編集部 https://hr.my-sol.net/contact/