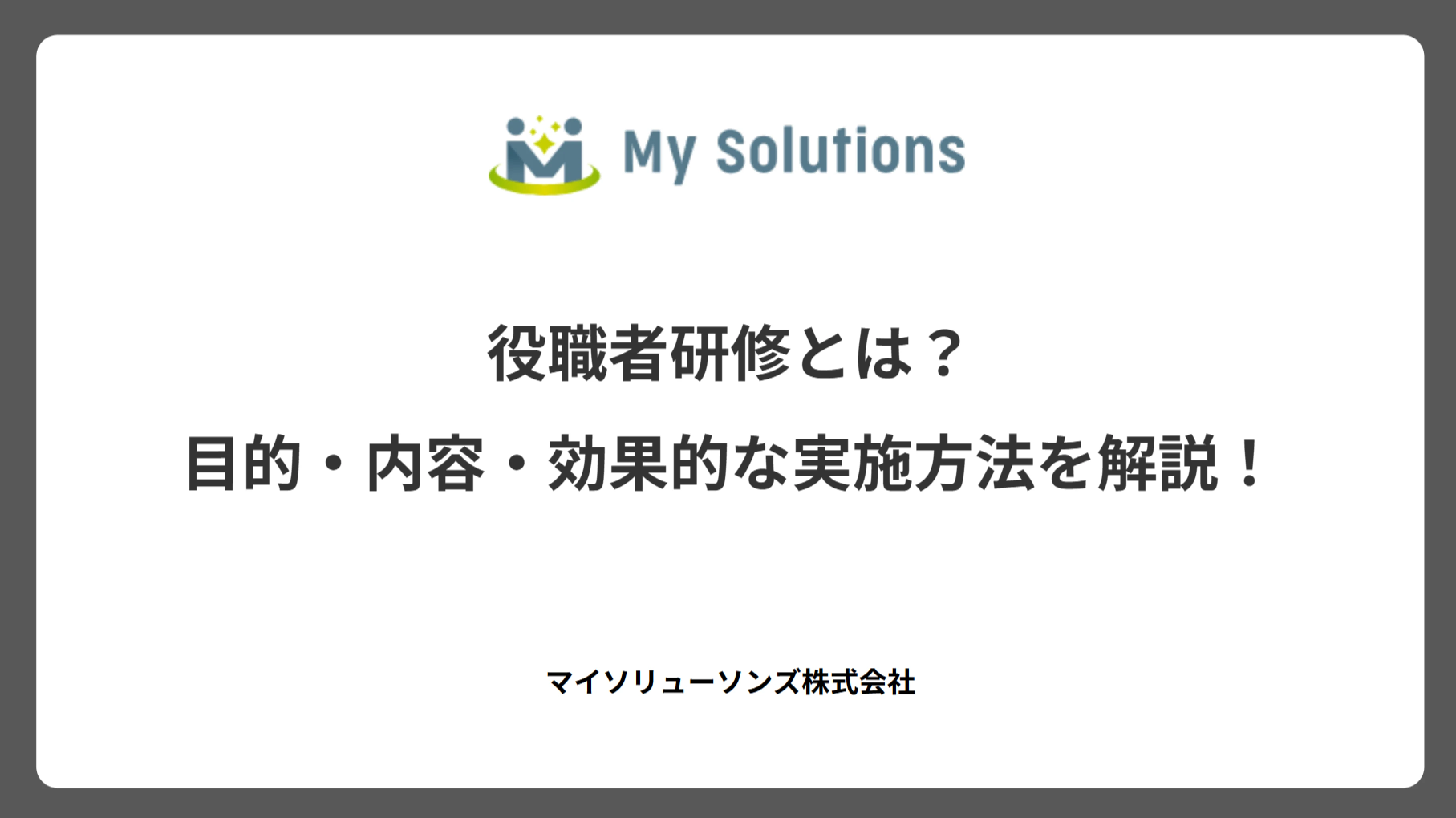記事公開日
最終更新日
【経営者必読・歴史に学ぶ組織論⑥】 なぜ聡明なリーダーは「致命的な欠陥」を見過ごすのか? 〜明治憲法・設計者の死角〜

はじめに:その「仕様」、本当に未来の成長を支えますか?
これまでの連載で、明治憲法が内包した「二重政府」という構造的欠陥が、いかに国家を危機に導いたかを見てきました。ここで、経営者なら誰もが抱くであろう素朴な疑問が浮かびます。「なぜ、伊藤博文をはじめとする聡明な設計者たちは、これほど致命的な問題に気づけなかったのか?」
彼らは決して無能だったわけではありません。むしろ、時代の制約の中で最善を尽くした天才たちでした。しかし、彼らには「死角」がありました。その死角は、「創業期の絶対目標」と「非公式な人間関係への依存」によって生まれます。これは、現代のあらゆる組織、特に創業期を乗り越えた成長企業が直面する課題そのものです。
第6回となる今回は、明治憲法の制定者たちの思考を追体験し、なぜ彼らが自ら「時限爆弾」を埋め込むに至ったのか、そのメカニズムを解き明かします。
第一回 なぜ巨大組織は「完璧な設計図」から崩壊したのか?〜明治憲法に学ぶ、創業期のビジョンと構造的欠陥〜
第二回 なぜ「エリート部署」の暴走を止められないのか? 〜明治憲法に学ぶ「二重政府」という組織の病〜
第三回 「犯人探し」で組織は変わらない。失敗を力に変える「構造的視点」とは?
第四回 「改善」か「革命」か?戦後日本、運命の分岐点 〜明治憲法・幻の改正案・現行憲法、3つの設計図を比較する〜
第五回 なぜ「非公式の重鎮」は組織を救い、時に壊すのか? 〜明治憲法の「元老」に学ぶ、相談役・顧問制度の功罪〜
第七回 なぜ外部の人間は「組織の病」をすぐに見抜けるのか? ~アメリカの慧眼と明治憲法~
死角①:「民主化」より「国家存続」が最優先だった
まず理解すべきは、彼らのゴール設定です。明治の指導者たちの最大のミッションは、個人の自由を保障する民主国家を作ることではなく、欧米列強の植民地化を免れ、不平等条約を改正するための「強い中央集権国家」を早急に作り上げることでした。
そのため、彼らはイギリスやフランスの自由主義的な憲法を「過激思想」として退け、君主の権力が強いプロイセン(ドイツ)憲法をモデルに選びました。これは、天皇を中心としたトップダウンの意思決定こそが、「富国強兵」を最速で実現する道だと信じたからです。
つまり、後に「欠陥」と指摘される天皇への権力集中や、議会の権限の弱さは、彼らにとっては意図された「仕様」だったのです。現代のスタートアップが、ガバナンスよりもまず市場での生き残りを最優先するのに似ています。目的が異なれば、最適な設計もまた変わるのです。
死角②:「統帥権の独立」は欠陥ではなく「安全装置」のつもりだった
本連載で繰り返し指摘してきた最大の構造的欠陥、「統帥権の独立」。軍部が政府のコントロールを受けずに暴走する原因となったこの規定も、制定者たちにとっては「良かれと思って」導入したものでした。
彼らが最も恐れたのは、西南戦争などの内乱の記憶から、軍隊が政争の道具となり、政治家の「私兵」と化すことでした。未成熟な政党政治の介入から軍の専門性と中立性を守り、天皇にのみ忠誠を誓う「国家の軍隊」とするために、あえて政治から切り離したのです。
これは致命的な計算違いでした。「政治に汚染された軍隊」のリスクを過大評価し、「誰にもコントロールされない軍隊」のリスクを過小評価してしまったのです。軍を「脱政治化」するための隔離措置が、皮肉にも軍を最強の政治集団へと変貌させる道を開いてしまいました。
死角③:憲法に書かれざる「自分たち」という究極の安全装置
では、なぜ彼らは「誰にもコントロールされない軍隊」のリスクを軽視できたのでしょうか。その答えは、第5回で考察した「元老」の存在にあります。
伊藤博文や山県有朋といった憲法の制定者たち自身が、憲法の条文には書かれていない「元老」として、国家の最終的な意思決定を担うことを想定していました。内閣と軍部が対立しても、議会が紛糾しても、最後は「俺たちが調整すればいい」という暗黙の前提があったのです。
元老たちは、憲法という公式なOSの上で動く、非公式の管理者権限(スーパーユーザー)でした。彼らが存命中は、この「人間系システム」が憲法の構造的欠陥を補い、国家のバランスを保っていました。しかし、このシステムは、特定の個人の功績と寿命に依存する、極めて属人的で再現性のないものでした。
彼らの最大の死角は、自分たちがいなくなった後の世界を具体的に設計しなかったことです。堅牢な組織とは、特定のカリスマがいなくてもルールと仕組みで自律的に機能するものです。しかし、明治の指導者たちは、自分たちの存在そのものを、国家運営の永続的な前提としてしまったのです。
結論:創業者の「暗黙知」が組織を蝕む
明治憲法の制定者たちが構造的問題に気づけなかった理由は、決して彼らが愚かだったからではありません。
- 至上命令: 「国家の生存」という絶対的な目標が、他の視点を曇らせた。
- 意図した設計: 後の「欠陥」は、当時の課題に対する「解決策」だった。
- 属人的システムへの依存: 憲法の不備を、自分たち「元老」という非公式な存在が補うことを当然視していた。
これは、現代の経営者にとっても他人事ではありません。創業期を支えた強力なリーダーシップや、創業者同士の「あうんの呼吸」は、組織が成長するにつれて機能不全に陥ります。「俺がいるから大丈夫」という過信が、仕組み(ガバナンス)の構築を遅らせ、次世代のリーダーが扱えない複雑な組織構造を残してしまうのです。
歴史は問いかけます。あなたの会社の成功を支えているのは、再現性のある「仕組み」ですか?それとも、いつかいなくなる「あなた」自身ですか?
👇👇動画解説はこちら👇👇
次回予告:
制定者たちが見過ごした欠陥を、なぜ海の向こうのアメリカは早くから見抜くことができたのでしょうか。それは、国家と軍隊に対する、根本的な哲学の違いに根差していました。
次回、第7回では、アメリカの視点から明治憲法を「健康診断」します。なぜ彼らは「二重政府」という病名を即座に診断できたのか。その洞察は、現代の私たちが自社の組織構造を客観的に評価するための、強力なレンズとなるでしょう。
第一回 なぜ巨大組織は「完璧な設計図」から崩壊したのか?〜明治憲法に学ぶ、創業期のビジョンと構造的欠陥〜
第二回 なぜ「エリート部署」の暴走を止められないのか? 〜明治憲法に学ぶ「二重政府」という組織の病〜
第三回 「犯人探し」で組織は変わらない。失敗を力に変える「構造的視点」とは?
第四回 「改善」か「革命」か?戦後日本、運命の分岐点 〜明治憲法・幻の改正案・現行憲法、3つの設計図を比較する〜
第五回 なぜ「非公式の重鎮」は組織を救い、時に壊すのか? 〜明治憲法の「元老」に学ぶ、相談役・顧問制度の功罪〜
第七回 なぜ外部の人間は「組織の病」をすぐに見抜けるのか? ~アメリカの慧眼と明治憲法~
編集者: マイソリューションズ編集部
https://hr.my-sol.net/contact/