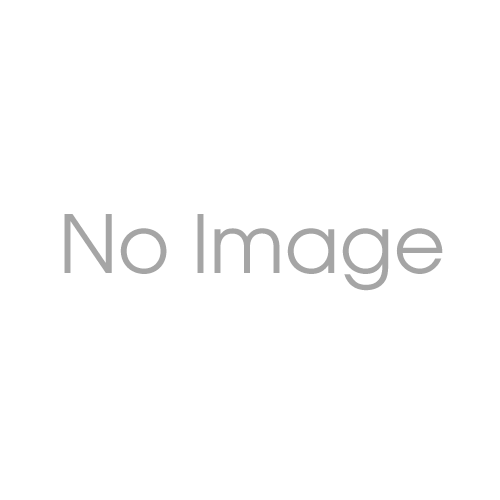記事公開日
最終更新日
親ガチャ・配属ガチャ・上司ガチャを言い訳にしない理論

親ガチャ・配属ガチャ・上司ガチャを言い訳にしない理論
親ガチャ・上司ガチャ・配属ガチャとは何か?
最近は「〜ガチャ」という言葉をよく耳にします。その言葉の由来はカプセルトイ販売機、いわゆる「ガチャガチャ」です。
お金を払って購入する権利を得たものの、ガチャガチャから何がでるかは「運任せ」です。
その特性を運の悪い人は「〜ガチャ」と名付けているのです。
代表的なガチャを紹介しましょう。
親ガチャとは
「親ガチャ」とは、子どもがどんな親の元に生まれるかは運任せであり、良い親の元に生まれるかどうかが、子どもの人生に大きな影響を与えるという状況を、スマホゲームのガチャに例えた言葉です。子どもは親を選ぶことができないため、まるでガチャを引くように、良い親(当たり)か、そうでない親(ハズレ)か、どちらに生まれるかは運任せだという考え方です。
上司ガチャとは
「上司ガチャ」とは、部下の立場から見て、上司が「当たり(良い上司)」か「ハズレ(悪い上司)」か、というように、上司の質をランダムに当たるガチャにたとえた言葉です。部下は上司を選べないため、このガチャに当たったかどうかが、その後のキャリアや仕事へのモチベーションに大きく影響すると感じられることから、この言葉が使われます。
配属ガチャとは
「配属ガチャ」とは、新卒で入社した際に、希望する部署や勤務地に配属されるかどうかわからない状況を、カプセルトイのガチャポンになぞらえて表現した言葉です。企業が新入社員の配属先を決定する際に、社員の希望や能力を必ずしも反映しない場合があり、その結果、新入社員は「アタリ(希望通り)」なのか「ハズレ(希望通りでない)」のかわからない状態に置かれることから、この言葉が使われるようになりました。
ガチャを肯定し、ガチャをコントロールする理論
皆さんは「計画された偶発性理論」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
私がこの言葉を初めて聞いたのは、2005年の冬でした。
当時私はGCDFキャリアカウンセラー資格を取得するためにキャリアカウンセラーの歴史と理論を学んでいました。
この言葉を聞いた時、私は「計画と偶発性って矛盾しているよね。どういうこと?」と思いました。
計画された偶発性理論とは
この理論は1999年にスタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授が提唱したキャリア理論です。
クランボルツ教授は多くの人生を研究し、人生に影響を与えた事象の8割は偶然だったことを突き止めました。
つまり人生は予測不可能という理論です。
自分が決めた目標に拘りすぎると目の前に訪れた幸運を逃しやすく、逆に目標にとらわれ過ぎず柔軟に構えていると幸運を手に入れやすい、と言っています。
人生の8割が偶然で決まるなら目標に向かって何かすることが無意味のように感じますが、それも違うとクランボルツ教授は言っています。
ガチャをコントロールする5つの行動特性
1)好奇心:何事にも好奇心をもって自ら情報をとりにいく
2)持続性:失敗しても簡単に諦めず継続して行動する
3)柔軟性:自分の考え方ややり方を柔軟に変えてみる
4)楽観性:失敗を成功の糧と前向きに捉える
5)冒険心:不確実性の高い道の高い領域に足を踏み入れる
目標に対して計画を固め過ぎず、100%偶然に身を委ねるわけでもなく、幸運が起きやすい自分でいる。これこそクランボルツ教授が導き出した成功への道標だったのです。
この理論の説明を聞いた時、私の頭に衝撃が走りました。一見すると矛盾している2つのことを統合して理論に昇華している。なんて素晴らしい柔軟と創造性なのだ、と。
イノベーションのジレンマとは
当時の私は「どうしたら『イノベーションのジレンマ』を乗り越えて、イノベーションを起こし続ける組織をつくれるのか」という問題に“勝手に“向き合っていました。
『イノベーションのジレンマ』とは、企業がイノベーションを起こそうと合理的に行動すると、その意図とは裏腹にイノベーションが起きないという現象を指します(1997年クレイトン・クリステンセン提唱)。
その主な理由は以下のとおりです。
・既存技術がある場合、それを捨てることができない(身内が競合になってしまう)
・新規市場は事前にマーケット調査できない(マーケットが存在しない)
・革新的な技術ほど将来性の判断が難しく、投資家に説明しにくい
ガチャから生まれたイノベーション
では、すでに世にあるイノベーションの数々はどうやって生まれたのか。
実は企業の合理的判断ではなく、個人の情熱や偶然によって起きている場合が多いのです。
例)ペニシリン、ポストイット、デジカメ、スマートフォン、バイアグラなど
大企業の経営者はこのジレンマを克服することが重要な課題であり、各企業で社運をかけて様々な試みがなされています。
計画された偶発性理論を知った時、すぐさまインスピレーションが湧いてきました。
「偶発性を織り込んだマネジメントを理論化しよう」と。
これが「動力マネジメント」が生まれた瞬間でした。