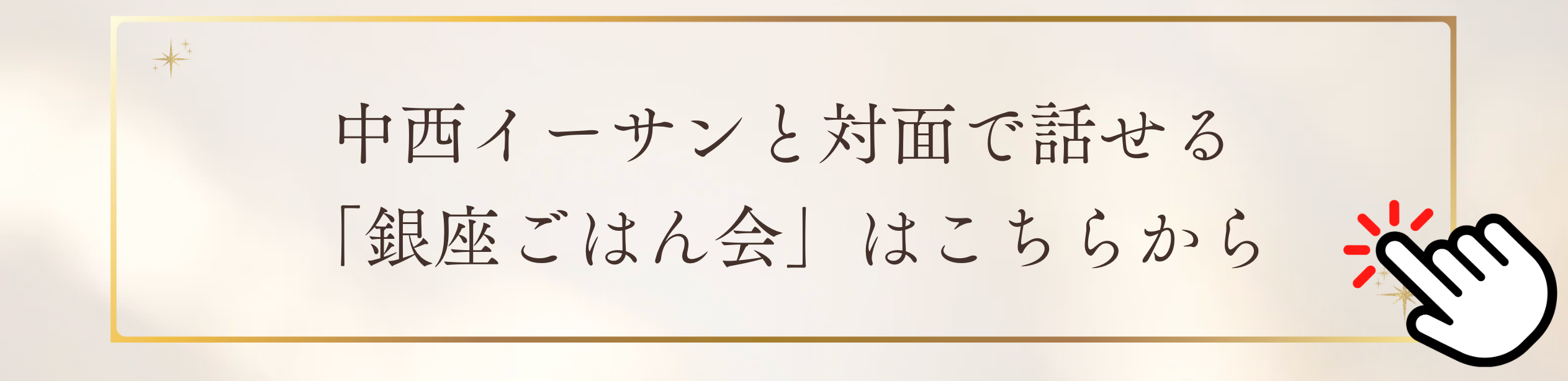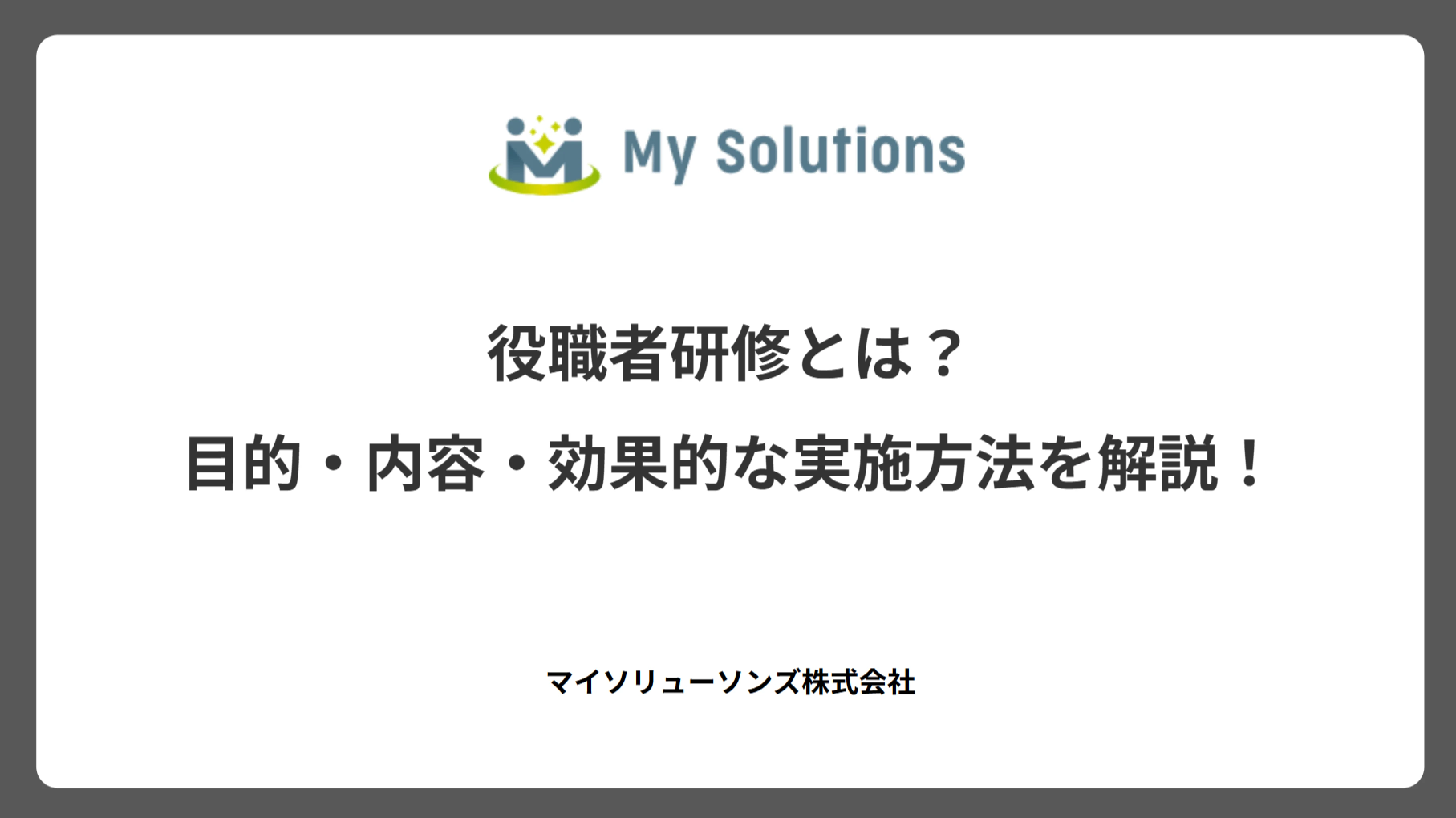記事公開日
NPS®とは?日本でスコアが低くなる理由と、ビジネスを成長させる活用戦略を徹底解説!

はじめに:顧客と従業員の「本音」を知る、新しいものさし
製品やサービスのコモディティ化(差別化が難しくなること)が進み、市場が成熟した現代。企業が持続的に成長するためには、単なる価格競争から抜け出すことが不可欠です。その鍵を握るのが、顧客や従業員との長期的な信頼関係、すなわち「ロイヤルティ」の構築です。特にSNSの普及により、個人の「おすすめ」や「残念な点」といった声は瞬く間に広がり、企業の業績を直接左右するほどの力を持つようになりました。
これまで多くの企業で使われてきた「顧客満足度(CS)」や「従業員満足度(ES)」といった指標は、その時々の短期的な感情を測るものでした。しかし、「満足している」という回答が、必ずしも将来の継続購入や会社への貢献につながるとは限らないことが、多くのデータで明らかになっています。
この課題を解決するために登場したのが、ネットプロモータースコア(NPS®)とエンプロイー・ネットプロモータースコア(eNPS®)です。これらの指標は、単なる満足度ではなく、「他の人にどれだけ勧めたいか?」という未来の行動につながる質問をすることで、企業の将来的な収益や成長と非常に強い関係があることが証明されています。欧米の先進企業では、すでに経営の重要な判断材料として活用されています。
この記事では、NPS®とeNPS®の基本からメリット・デメリット、そして「なぜ日本ではスコアが低く出やすいのか?」という疑問までを深掘りします。その上で、日本企業がこの強力なツールを使いこなし、競争力を高めるための具体的な戦略をご紹介します。
NPS®の基本:顧客満足度との違いとメリット・デメリット
1.1. NPS®とは?「究極の質問」で顧客ロイヤルティを測る
NPS®は、顧客ロイヤルティを測るために2003年に開発された指標です。基本は、たった一つの「究極の質問」に基づいています。
「あなたはこの企業(製品/サービス)を親しい友人や同僚にどの程度推奨したいと思いますか?」
顧客はこの質問に対し、0(全く推奨したくない)から10(非常に推奨したい)までの11段階で評価します。この回答によって、顧客は3つのタイプに分類されます。
- 推奨者 (Promoters): 9~10点を付けた顧客。熱心なファンであり、積極的に他者へ勧めてくれる存在です。
- 中立者 (Passives): 7~8点を付けた顧客。満足はしているものの、より良い選択肢があれば他社に乗り換える可能性があります。
- 批判者 (Detractors): 0~6点を付けた顧客。何らかの不満を抱えており、ネガティブな口コミを広める可能性があります。
NPS®スコアは、以下のシンプルな計算式で算出されます。
NPS® = 推奨者の割合(%) - 批判者の割合(%)
スコアは-100から+100の範囲で表され、高いほど顧客ロイヤルティが高いことを示します。
1.2. 顧客満足度(CS)との決定的な違いは「未来を予測する力」
NPS®と顧客満足度(CS)は似ているようで、本質が大きく異なります。CSが「短期的な評価」であるのに対し、NPS®は企業全体への「長期的な愛着や信頼(ロイヤルティ)」を測定します。
衝撃的なデータとして、「サービスを解約した顧客の80%が、直前のCS調査で『満足』と回答していた」という報告もあります。つまり、「満足」は必ずしも未来の行動を約束しないのです。
一方、NPS®は将来の購買行動やリピート率と強い相関があることが証明されています。なぜなら、「他人に勧める」という行為には、自分の評判をかけるという責任が伴うため、単なる満足よりも強い意志が必要だからです。この「未来の収益性を予測する力」こそ、NPS®が経営指標として注目される最大の理由です。
表1:NPS®と顧客満足度(CS)の比較
| 比較軸 | NPS®(ネットプロモータースコア) | 顧客満足度(CS) |
|---|---|---|
| 測定対象 | 企業やブランドへの長期的なロイヤルティ(愛着・信頼) | 特定の製品・サービスへの短期的な満足度 |
| 質問形式 | 「他者への推奨意向」を問う未来志向の質問 | 「自身の満足度」を問う過去志向の質問 |
| 収益性との相関 | 強い相関があり、事業成長の先行指標となる | 相関は必ずしも強くない |
1.3. NPS®活用のメリット
NPS®を導入することで、企業は多くのメリットを得られます。
- 事業成長との強い相関: NPS®が高い企業は、競合の2倍の成長率を上げているというデータもあります。NPS®は将来の業績を予測する先行指標として機能します。
- シンプルで分かりやすい: 質問がシンプルで計算も簡単なため、専門知識がなくても導入できます。全社共通の目標(KPI)として設定しやすいのも魅力です。
- 競合他社との比較が可能: 世界共通の指標なので、業界内での自社の立ち位置を客観的に把握し、戦略を立てるのに役立ちます。
- 具体的な改善点が見つかる: 「そのスコアを付けた理由」を自由回答で尋ねることで、顧客の「生の声」から改善のヒントを得られます。この定性的なフィードバックこそが宝の山です。
1.4. NPS®の注意点とよくある失敗
多くのメリットがある一方、注意すべき点もあります。
- スコアだけでは意味がない: なぜそのスコアなのか?という背景を、自由回答などから深く理解することが不可欠です。
- 文化的なバイアス: 国や地域によって評価の付け方が異なります。特に日本ではスコアが低く出やすい傾向があり、海外との単純比較は危険です。
- スコアを上げること自体が目的化する: 最も危険なのが、スコアを上げること自体が目的になってしまうことです。顧客体験の根本的な改善を怠り、表面的な対策に走ってしまうと、NPS®導入は失敗に終わります。
NPS®の真の価値は、スコアという結果そのものではなく、顧客の声をもとに改善を続ける「仕組み(プロセス)」を社内に作ることにあるのです。
eNPS®とは?従業員のエンゲージメントを高め、離職を防ぐ方法
2.1. eNPS®の基本:従業員の「本音」を引き出す指標
eNPS®は、NPS®を従業員向けに応用したものです。「あなたの現在の職場を、親しい友人や知人にどの程度勧めたいですか?」という質問で、従業員の会社に対するエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を数値化します。
この指標は、Apple社が社内で活用したことから広く知られるようになりました。計算方法はNPS®と全く同じです。
従来の従業員満足度(ES)調査との違いは、ここでも「本音の引き出しやすさ」にあります。「満足していますか?」という直接的な質問よりも、「大切な人に勧められますか?」という間接的な質問の方が、より正直な気持ちが表れやすいのです。
2.2. eNPS®導入のメリット:離職率低下から採用力強化まで
eNPS®を高めることは、企業経営に大きなプラスの効果をもたらします。
- 離職率の低下: eNPS®スコアと離職率には明確な関係があります。「批判者」は離職リスクが非常に高いことが分かっており、彼らの不満を早期に発見し対処することで、優秀な人材の流出を防ぐことができます。
- 生産性の向上: エンゲージメントの高い従業員は、自発的に仕事に貢献しようとします。その結果、組織全体の生産性が向上します。
- 採用力の強化: 「推奨者」である従業員は、会社の魅力を外に伝えてくれる「歩く広告塔」です。社員紹介(リファラル採用)が活発になり、採用コストを抑えつつ、ミスマッチの少ない優秀な人材を確保できます。
- 顧客満足度(NPS®)の向上: 従業員のエンゲージメントが高まると、顧客へのサービス品質も向上します。その結果、顧客ロイヤルティ、つまりNPS®の向上にもつながるという好循環が生まれます。
2.3. 導入の注意点:「やりっぱなし」は逆効果!
eNPS®で最も注意すべきは、調査を「やりっぱなし」にしないことです。従業員から声を集めたにもかかわらず、何も改善が行われなければ、「どうせ言っても無駄だ」と、かえって従業員のエンゲージメントを下げてしまいます。
重要なのは、調査結果を真摯に受け止め、課題の根本原因を特定し、具体的な改善策を実行し、その進捗を従業員にフィードバックするというサイクルを回し続けることです。eNPS®は、従業員と会社が共に成長するための戦略的エンジンなのです。
なぜ日本のNPS®は低い?文化的背景と3つの普及障壁
NPS®やeNPS®は非常に有効なツールですが、日本では欧米ほど普及していません。その背景には、日本の文化に根差した特有の障壁があります。
3.1. 「マイナススコアの謎」:日本人の回答傾向
日本でNPS®調査を行うと、優良企業でさえスコアがマイナスになることがよくあります。この「マイナススコアの謎」は、日本人のアンケート回答のクセに原因があります。
- 真ん中を選びやすい傾向: 日本人は「とても良い」「全く悪い」といった極端な評価を避け、「どちらともいえない」といった中間的な選択肢を好む傾向があります。
- 評価スケールのミスマッチ: NPS®では0~6点が「批判者」に分類されます。日本人は11段階評価の真ん中として「5」を選びがちですが、悪気なく付けた「5点」や「6点」が、システム上は「批判者」としてカウントされてしまうのです。これが、日本のスコアが構造的に低くなる大きな原因です。
3.2. 「推奨」への心理的ハードル
もう一つの深層的な要因は、「友人への推奨」という行為が持つ重みです。人に何かを勧めることは、自分の評判を賭ける行為でもあります。もし勧めたものが友人を満足させられなかったら…という人間関係のリスクを考えると、たとえ自分は満足していても、他人への推奨には慎重になりがちです。この心理的なブレーキが、スコアを控えめにさせる一因となっています。
3.3. 経営層の誤解と短期的な成果主義
こうした文化的背景を知らないと、経営層はマイナスのスコアを見て「うちのサービスはダメだ」と落ち込んだり、「この指標は日本では意味がない」と結論付けてしまったりします。スコアの「絶対値」に一喜一憂するのではなく、「時系列での変化」や「競合との相対比較」を見ることが重要なのですが、この点が理解されにくいのが現状です。
また、NPS®に基づく改善活動は効果が出るまでに時間がかかります。四半期ごとの売上など短期的な成果を重視する企業文化の中では、長期的なロイヤルティ構築への投資は後回しにされがちです。
表2:日本特有の回答バイアスとNPS®スコアへの影響
| バイアスの種類 | NPS®回答における具体的な現れ方 | スコアへの影響 |
|---|---|---|
| 中間回答傾向 | 11段階評価の中間点である「5」周辺に回答が集中しやすい。 | 「5点」「6点」は「批判者」に分類されるため、批判者の割合が構造的に増加し、スコアが大幅に低下する。 |
| 極端回答の回避 | 非常に満足していても、満点の「10点」を付けることにためらいを感じ、「8点」や「9点」を選ぶ傾向がある。 | 「推奨者」となる「9点」「10点」の回答率が低くなり、スコアが伸び悩む。 |
| 推奨への慎重姿勢 | 満足していても、他人への推奨には責任が伴うため、評価を一段階下げて回答する(例:満足だが6点を付ける)。 | 満足している顧客が「批判者」として誤って分類され、真のロイヤルティが過小評価される。 |
日本企業がNPS®/eNPS®で成功するための3ステップ戦略
日本特有の課題を乗り越え、NPS®/eNPS®を経営に活かすための具体的なアクションプランを3つのステップで提案します。
ステップ1:意識改革と基盤構築(導入〜6ヶ月)
1. 経営層の理解を得る:「絶対値」ではなく「変化」を見る
まず、経営層に「日本のスコアは低く出やすい」という事実を理解してもらうことが最重要です。注目すべきはスコアの絶対値ではなく、以下の3点であることを共有しましょう。
- 時系列での推移: 前回の調査からスコアが改善したか? たとえマイナスでも、改善傾向にあればそれは「成功」です。
- 国内競合との相対比較: 業界内での自社のポジションを把握します。
- スコアの内訳: 批判者を減らし、推奨者を増やすことが目標であることを明確にします。
2. 目的を明確にする:何のために測るのか?
「解約率を5%下げる」「若手社員の離職率を改善する」など、具体的な事業課題と結びつけて目標を設定します。目的が明確になれば、調査のタイミングや質問内容も自然と決まります。
3. 部門横断チームを作る
顧客体験や従業員体験は、一つの部署だけでは改善できません。営業、開発、サポート、人事など、関連部署のメンバーを集めた部門横断的な推進チームを立ち上げることが成功の鍵です。
ステップ2:実践とデータ活用(6ヶ月〜2年)
1. 調査設計を最適化する:「生の声」を重視する
スコアを問う質問と合わせて、必ず「そのスコアを付けた理由」を自由回答で尋ねましょう。顧客や従業員の「生の声」こそが、改善のヒントの宝庫です。また、推奨度に影響する要因(価格、品質、サポート体制、上司との関係など)を特定するための質問を追加するのも有効です。
2. 「クローズドループ」を徹底する:フィードバックに必ず応える
NPS®/eNPS®活用の心臓部が、フィードバックを受けて改善サイクルを回す「クローズドループ」です。
- 個別対応: 特に批判的なフィードバックをくれた顧客や従業員には、担当者が迅速に連絡を取り、話を聞きます。この真摯な対応が、不満を抱いた相手をファンに変える最大のチャンスです。
- 根本改善: 個別の声から共通の課題を見つけ、製品や業務プロセス、社内制度の改善につなげます。このPDCAサイクルを組織的に回し続ける仕組みを作りましょう。
ステップ3:組織文化への昇華(2年〜)
1. 全社で共有し、成功体験を広める
調査結果や改善の成果を、社内の誰もが見える形で定期的に共有します。特に、改善活動が売上向上や離職率低下につながった成功事例を共有することで、「顧客や従業員の声を聞くことは、自分たちの成功につながる」というポジティブな文化を醸成します。
2. eNPS®とNPS®を連携させる
従業員体験の向上(eNPS®向上)が、顧客体験の向上(NPS®向上)につながるという「サービス・プロフィット・チェーン」の考え方を、実際のデータで示しましょう。従業員への投資が業績向上に貢献するという事実が証明できれば、取り組みはさらに加速します。
3. 人事評価に反映させる
最終的には、ロイヤルティ向上への貢献度を個人の業績評価などに組み込むことを検討します。これにより、顧客や従業員を大切にする行動が、単なる「良いこと」から「評価されるべき仕事」へと変わり、顧客・従業員中心の文化が組織に根付いていきます。
表3:NPS®/eNPS®導入・定着化ロードマップ
| 関係者 | ステップ1:意識改革と基盤構築 | ステップ2:実践とデータ活用 | ステップ3:組織文化への昇華 |
|---|---|---|---|
| 経営層 | ・NPS®/eNPS®の目的と重要性を全社に発信 ・スコアの絶対値ではなく「変化」を重視する方針を明示 |
・改善アクションに必要なリソースを承認 ・定期的に進捗を確認し、フィードバック |
・ロイヤルティ向上への貢献を経営陣の評価にも反映 ・顧客・従業員中心の企業文化を体現する |
| 推進チーム | ・部門横断チームを組成 ・導入目的と目標を設計 ・第1回目の調査を実施・分析 |
・定期的な調査と詳細な分析を実施 ・クローズドループの仕組みを構築・運用 |
・全社への定期的な結果・成果共有 ・成功事例の収集と横展開 ・eNPS®とNPS®の相関分析と戦略提言 |
| 現場部門 | ・NPS®の概念と自部門の役割を理解 ・自部門の課題を把握 |
・批判者への迅速なフォローアップ体制を構築 ・フィードバックを基に業務プロセスを改善 |
・自部門のNPS®スコアに責任を持つ ・顧客の声を起点とした自律的な改善を実践 |
| 人事部門 | ・eNPS®の概念と目的を管理職へ研修 ・全社的な組織課題を特定 |
・eNPS®の属性別分析を実施 ・スコアが低い部門の改善を支援 ・課題(例:評価制度)に対する改善策を実行 |
・eNPS®改善への貢献度を管理職の評価に導入 ・採用や研修にeNPS®の知見を活用 |
まとめ:スコアの先にある「対話」と「成長」へ
NPS®とeNPS®は、単に数値を測るだけのツールではありません。企業の未来を創り出すための戦略的な羅針盤です。日本市場には特有の難しさがありますが、それを正しく理解し、スコアの絶対値に一喜一憂するのではなく、その「変化」を追い、背景にある「声」に真摯に耳を傾けることが重要です。
そして、その声に基づいて行動し、改善のサイクルを回し続ける。この「日本型NPS®/eNPS®運用モデル」を構築できた企業は、顧客と従業員の両方から深く愛され、信頼される強固な基盤を築くことができるでしょう。
NPS®/eNPS®の導入は、組織全体が常に対話し、学び、改善し続ける「学習する組織」へと変わっていくための、壮大な変革の旅です。この終わりなき旅こそが、不確実な未来を生き抜くための、最も確かな道筋となるのではないでしょうか。
NPS®やeNPS®を成功させる鍵は、顧客や従業員の声に耳を傾け、組織全体で改善に取り組む文化を育むことです。マイソリューションズでは、こうした組織文化の醸成や人材育成をサポートする多様な研修プログラムや、役立つコラムを多数ご用意しています。貴社の成長のヒントを見つけに、ぜひ一度ご覧ください。
編集者: マイソリューションズ編集部 https://hr.my-sol.net/contact/