記事公開日
最終更新日
TSMC研究三部作:世界の半導体を支える巨人の深奥に迫る(第二部)
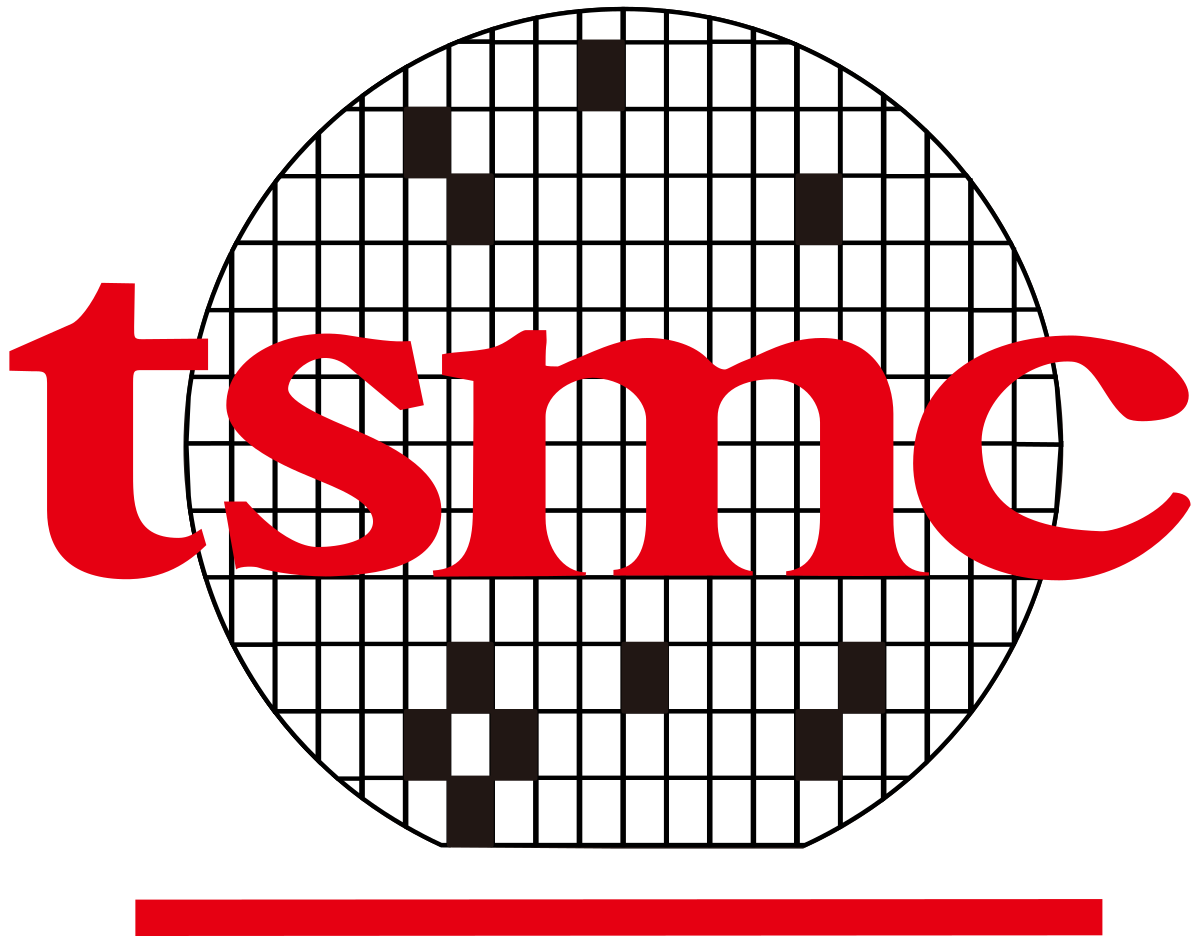
TSMC研究:世界を動かす半導体巨人の全貌
「第一部:TSMCの軌跡:半導体産業の礎を築いた巨人」はこちら
はじめに:現代社会を支えるTSMCの存在
現代のデジタル化された社会において、半導体はまさにその心臓部を形成しています。スマートフォンから人工知能(AI)システム、自動運転車、そして大規模なデータセンターに至るまで、あらゆる最先端技術の根幹には高性能な半導体の存在が不可欠です。この半導体産業において、台湾積体電路製造(TSMC)は、単なる一企業という枠を超え、世界のテクノロジーエコシステムを支える基盤的な役割を担っています。TSMCは、独自のビジネスモデルと卓越した技術力によって、半導体産業の構造そのものを変革し、今日のデジタルイノベーションを牽引する「巨人」として君臨しています。その足跡を辿ることは、現代社会の技術的進化の裏側にある重要な物語を解き明かすことに他なりません。

第二部:TSMCの技術革新と未来への展望
第4章:最先端プロセス技術の進化
TSMCの競争優位性の核は、常に業界をリードする最先端プロセス技術の開発と量産能力にあります。微細化の限界に挑み続けることで、同社は半導体性能の飛躍的な向上を牽引しています。
N3プロセス(3nm)の詳細と用途
TSMCのN3プロセス(3nm)は、2022年後半に量産体制が整えられました。このノードでは、月間3万~3万5000枚のチップ生産が予定されており、主にハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)とスマートフォン向けに利用されています。N3プロセスは、N5ノードと比較して消費電力を25~30%削減し、同じ電力でのパフォーマンスを10~15%向上させるなど、大幅な性能向上が実現されています。また、N3プロセスには「N3E」「N3P」「N3S」「N3X」といった複数の派生ノードが存在し、顧客の多様なニーズに対応しています。特にN3Eは、N3よりも広いプロセスウィンドウと高い歩留まりを提供し、より汎用性の高いノードとして多くの「3nmテープアウト」を記録しています。
N2プロセス(2nm)とGAAFET技術
TSMCは、次世代のN2プロセス(2nm)において、従来のFinFET技術から「ゲートオールアラウンド(GAA)」技術への移行を明確にしています。N2ノードのリスク生産は2024年末に行われ、2025年末に向けて量産体制が整い、2026年頃に市場に出回ると予想されています。
GAAFET技術は、FinFETのヒレ状のチャネルを水平に積み重ねた「ナノシート」に変え、ゲートがチャネルの周囲を完全に包み込む構造です。これにより、FinFETの三方からの包み込みと比較して、より優れた静電制御能力を提供し、リーク電流を効果的に抑制できます。N2プロセスでは、現行の3nmプロセスと比較して最大30%の電力効率向上または15%の性能向上を実現するとされています。また、「N2 NanoFlex」と呼ばれる設計技術により、ナノシートの幅を自由に調整できるため、チップ設計の柔軟性が大幅に向上し、より細やかな性能最適化が可能になります。
1.4nm(A14)および1.6nm(A16)のロードマップと特徴
TSMCは、2nmプロセス以降の技術ロードマップとして、N2P、A16(1.6nm級)、そしてA14(1.4nm級)を計画しています。
- N2P: N2の改良版で、電力効率などをさらに改善したものです。
- A16(1.6nm級): GAAトランジスタ構造を採用し、チップ背面に電力供給ネットワークを配置する「バックサイドパワーデリバリー」を導入する予定です。これはHPC/AIアプリケーションに最適化されており、革新的な裏面電源ソリューションを提供します。
- A14(1.4nm級): 2028年からの量産開始を目指しており、N2プロセスと比較して最大15%の処理速度向上、最大30%の電力削減、ロジック密度20%以上の向上を実現するとされています。A14は、電池寿命と熱管理が重要なモバイル機器やエッジ・コンピューティングに最適であり、AIの進歩において物理世界とデジタル世界をつなぐ最先端ソリューションの一部を形成すると期待されています。
これらの次世代プロセスの生産拠点は、台湾の新竹Fab 20、高雄Fab 22、台中Fab 25に加え、米国アリゾナ州のFab 21でもA16/N2プロセスに対応する第3期工場の建設が開始されています。
第5章:先進パッケージング技術と3D積層
半導体の性能向上は、単なる微細化だけでなく、複数のチップを効率的に統合する先進パッケージング技術によっても大きく推進されています。TSMCは、この分野でも業界をリードする技術を開発しています。
CoWoSおよびInFO技術の概要とメリット
TSMCは、CoWoS®(Chip-on-Wafer-on-Substrate)およびInFO(Integrated Fan-Out)といった先進パッケージング技術を提供しています。
- CoWoS®: 複数のチップをシリコンインターポーザー上に配置し、高帯域幅の接続を実現する技術です。特にHPCやAI向けチップにおいて、優れた性能と高い信頼性を提供します。CoWoS-Lは、CoWoS®-SとInFO技術の利点を融合した「チップ後付け(chip-last)」方式のパッケージであり、ローカルシリコンインターコネクト(LSI)やモールドベースのインターポーザー、Deep Trench Capacitor (eDTC)の統合により、高密度なダイ間インターコネクト、高速信号伝送時の高周波信号損失低減、電力管理の向上を実現します。
- InFO: パッケージ基板を用いず、チップの外側に再配線層(RDL)を拡張した構造を持つ技術です。これにより、数多くの入出力数に対応可能となり、チップを薄くできる、製造コストを低減できる、配線長が短くなることで信号の伝送速度を高速化できるといったメリットがあります。
これらの技術は、SoC-to-SoC、SoC-to-Chiplet、SoC-to-High Bandwidth Memory(HBM)といった多様な接続アーキテクチャに対応し、AIやHPCの需要の高まりに応える重要な役割を担っています。
SoIC技術の詳細とHPC/AIチップへの影響
TSMCのSoIC(System on Integrated Chips)は、複数のチップを垂直方向に積層することで、高密度な接続を実現し、システム全体の性能を向上させる最先端の3D ICパッケージング技術です。
- 特徴: 異なる機能やサイズのチップを一つのパッケージ内で積層し、集積度を高めます。特に10ナノメートル以下の先進プロセスにおいて、ウェハレベルでの接合技術を用いています。これにより、トランジスタ密度の増加と消費電力の削減が実現され、性能に対するエネルギー効率が向上します。SoICは、従来の2D ICや2.5D IC技術を超える3D IC技術の一形態であり、チップ間の通信速度と帯域幅を大幅に向上させます。
- HPC/AIチップへの影響: HPCやAI向けチップは、その高い性能ゆえに大量の熱を発生させるため、SoIC技術による高密度な積層と放熱性能の向上は、これらのチップの安定稼働と性能維持に不可欠です。高密度な積層は、チップ間のデータ転送効率を高め、HPCやAIアプリケーションの処理能力をさらに向上させることに貢献します。
- 主要顧客の採用: Appleは2025年下半期にSoIC技術の採用を見込んでおり、NVIDIAは2028年に採用を予定しています。TSMCはSoIC技術の生産能力を2026年までに現在の20倍以上に拡大する計画を立てており、これによりAMDなどの大口顧客への供給も強化される見込みです。
3Dスタッキング技術の課題と展望
3D積層型NAND型フラッシュメモリの技術的特徴は、メモリセルを垂直方向に多層に積層することで高密度化を実現することにあります。しかし、高積層構造を形成するプロセス技術の高コスト化が大きな課題となっています。積層数の増加に伴い、必要な装置台数が増加し、多額の追加投資が必要となるため、将来的には高積層化によって大容量化しても低コスト化しない懸念があります。
TSMCは、ロジックデバイスの分野で3次元構造トランジスタであるGAAFETの実用化を2nm世代から進めており、将来的にCMOS回路を薄膜化して積層する「3D集積回路構造」への突入を目指しています。チップの張り合わせによる機能積層による3Dパッケージング技術により、1mm²あたり百万個超の張り合わせ接続も期待されています。これらの技術革新は、半導体性能のさらなる飛躍を可能にする一方で、製造コストや技術的な複雑さといった課題の克服が求められます。
第三部:TSMCの企業文化、持続可能性、そして世界への影響
第6章:企業文化とイノベーション哲学
TSMCの持続的な成功は、その卓越した技術力だけでなく、独自の企業文化とイノベーション哲学に深く根ざしています。これらは、同社が顧客との強固な関係を築き、変化の激しい半導体業界で常に先頭を走り続ける原動力となっています。
「ICIC」のコア・バリュー
TSMCの企業文化は、「ICIC」という4つのコア・バリューに集約されています。
- Integrity(誠実、正直): 最も基本的で重要な価値観であり、真実のみを語り、達成した実績のみを企業価値の証とします。公正な競争を行い、他社の知的財産を尊重し、いかなる不道徳な行為も容認しません。
- Commitment(責任、約束): 顧客、協力会社、社員、株主、そして社会の繁栄を約束し、一度コミットメントしたことは最後まで貫徹するよう努力します。
- Innovation(イノベーション): 成長の源泉であり、単なる新しい発案に留まらず、それを実際に実行することを意味します。戦略立案から技術、製造に至るまで、事業のあらゆる面でたゆまぬ改革を追求します。
- Customer focus(顧客中心): 顧客をパートナーと位置付け、顧客とは絶対に競争せず、顧客の競争力向上をTSMC自身の競争力向上と見なします。顧客の成功がTSMCの成功であるという哲学を貫いています。
これらの価値観は、TSMCが長期的な視点でビジネスを運営し、顧客からの信頼を築く上で不可欠な基盤となっています。
顧客との「共同成長モデル」
TSMCのイノベーション哲学の根幹には、顧客との「共同成長モデル」があります。同社は、R&D能力、製品の品質、過去の経営パフォーマンスから潜在力のある顧客を見つけ出し、長期的に育成するポリシーを徹底しています。顧客が設立初期で規模が小さい場合でも、合理的で有意義なビジネスプランを提出し、製品開発能力や技術力、販売計画、チームワークなどを最優先に考慮して試行の機会を与えます。
この「共同成長モデル」と長期的な「育成の協力関係」により、顧客は他社ではなくTSMCを選択するようになり、TSMCの顧客は絶えず増え続けています。このモデルを通じて、TSMCはATi、nVidia、Marvell、Broadcom、Silicon Labなど、後に大企業に成長した多くの企業を育成し、同時に自らのR&D能力も成長させてきました。これは、競争ライバルが模倣できない独創的な「勝利の方程式」を構築したと言えるでしょう。
研究開発への投資と技術的独立性
TSMCは、技術的リーダーシップを維持するために、研究開発(R&D)に惜しみない投資を行っています。20年近くにわたり、売上高の8%を研究開発費に投じており、現在の年間研究開発費は55億ドルに達しています。これは、米マサチューセッツ工科大学の年間予算20億ドルをはるかに上回る額です。
この巨額な投資は、回路線幅2nm以下の先端半導体、高速コンピューティング、人工知能(AI)サービス、自動運転、裸眼3D技術など、幅広い先端技術の探求に充てられています。創業者のモリス・チャン氏の時代から、TSMCは技術的に独立する道を志向し、世界の大手メーカーの特許に干渉されないよう、技術面で自立することに注力してきました。7nmプロセスの半導体の量産までには30年かかりましたが、この長年の努力が現在の世界をリードする地位を確立しました。
2023年7月には台湾にグローバルR&Dセンターを開設し、台湾を技術開発の拠点とし続ける強い決意を示しています。このセンターは、今後20年間で従来型コンピューターと量子コンピューター技術の統合を探究し、革新を続けることでリーダーの地位を維持することを目指しています。
第7章:財務実績と持続可能性への取り組み
TSMCは、その堅調な財務実績と、環境・社会・ガバナンス(ESG)への積極的な取り組みによって、持続可能な成長を追求しています。
近年の財務実績(売上高、純利益、配当)
TSMCの財務実績は非常に堅調です。2024年の連結売上高は2兆8,943億1,000万台湾ドルに達し、2023年から33.9%増加しました。純利益は1兆1,732億7,000万台湾ドルで、2023年から39.9%増加しています。米ドル換算では、連結売上高は900億8,000万米ドル、純利益は365億2,000万米ドルでした。
粗利益率は56.1%、営業利益率は45.7%、純利益率は40.5%と、高い収益性を維持しています。総ウェーハ出荷量は1,290万枚(12インチ換算)に増加し、先端技術(7ナノメートル以降)が総ウェーハ売上高の69%を占めるなど、高付加価値製品へのシフトが進んでいます。
配当政策においては、TSMCは持続可能な配当の確保を重視しており、2024年の現金配当総額は1株当たり14.0台湾ドルに引き上げられました。2004年に配当を開始して以来、一株当たりの配当金が減額されたことはなく、年間および四半期ベースで安定した配当を確保しています。
ESG戦略と環境目標(カーボンニュートラル、水資源、廃棄物)
TSMCは、企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組み、ESG(環境・社会・ガバナンス)を経営の重要な柱として位置づけています。
環境目標:
- カーボンニュートラル: 2025年までに温室効果ガス排出量ゼロ成長を達成し、2050年にはネットゼロを目指しています。この目標達成のため、2016年に省エネ・脱炭素委員会を設立し、2017年には再生可能エネルギープロジェクト、2019年にはカーボン・クレジット開発プロジェクトを立ち上げました。
- 水資源管理: 2021年から再生水の使用を開始しており、2030年までには製造工程で使用する水の60%を再生水とすることを目指しています。また、ウェハー製造設備と製造工程を見直すことで、水使用効率を39%向上させることを目標としています。TSMCは台湾で初めて再生水工場を建設し、南部サイエンスパーク管理局の汚水処理場の放流水を再生水として利用しています。
- 廃棄物管理: 半導体製造工程の副産物を再利用することで、廃棄物の処理委託を年間13万トン減らすことを目指しています。これは中科工場の廃棄物の85%以上に相当し、環境コストを15億台湾元削減できるとされています。将来的には、南部科学園区や海外にもゼロウェイストセンターを設立する計画です。また、バックグラインド工程からの廃水リサイクルプロジェクトも推進しており、有害化学物質を使用しない物理法での資源回収を行い、シリコン素材や二次利用水を回収しています。
TSMCは、これらの取り組みを「TSMCサプライヤー・サステナビリティ・アカデミー」を通じてサプライヤーと共有し、業界全体のネットゼロへの貢献を促しています。
サプライチェーンのリスク管理と品質方針
TSMCは、グローバルなサプライチェーンにおけるリスクを最小限に抑えるため、能動的かつ強固な全社的リスクマネジメント(ERM)システムを維持しています。
リスク管理戦略:
- 直面するリスクを把握し、リスク選好およびリスク許容度の範囲内で確実に管理すること。
- 機会を効果的に活用し、潜在リスクを最小限にするために、企業の成長戦略にフォーカスしたリソースの優先順位を決定すること。
- 最終的に企業価値の創造につなげること。
TSMCはERMの枠組みに基づいてリスクの特定、評価、対応、モニタリング、レビューを行い、経営陣が十分な情報に基づいて経営判断を行えるようにしています。これには、リスクに対して意識的な文化、リスクガバナンス、企業運営と統合されたリスクマネジメントプロセス、組織の枠組みを超えた連携および継続的改善が含まれます。サプライチェーンにおけるリスクを最小限に抑えるため、資材管理、ファブ運営、リスク管理、品質管理を一体化して管理し、サプライヤーとの連携強化も図っています。
品質方針:
TSMCの品質方針は以下の通りです:
- 世界中のお客様に卓越した半導体製造サービスを提供し、双方にとって有益で長期的なパートナーシップを築くために全力を尽くします。
- 品質への真摯な姿勢を組織全体に浸透させ、顧客満足度を維持するために継続的な改善の文化を確立します。究極の目標はゼロディフェクトです。
- 適切な封じ込めプログラムを実施し、欠陥がなくなるまで、不良品からお客様を守ります。全員がこの目標を達成する責任を共有しています。
TSMCの品質管理システムは、ISO 9001、Ford Q1 award、QS-9000、ISO/TS 16949、IECQ QC 080000など、様々な国際品質基準に基づいています。
第8章:未来への展望と社会への貢献
TSMCは、単なる半導体製造企業に留まらず、その技術とビジネスモデルを通じて、世界のテクノロジーエコシステムと社会全体に多大な貢献をしています。
テクノロジーエコシステムへの貢献と人材育成
TSMCは、業界をリードするプロセス技術と設計支援ソリューションのポートフォリオを通じて、世界中の顧客とパートナーからなる拡大するエコシステムをサポートし、半導体業界にイノベーションをもたらしています。同社の革新的なビジネスモデルは、IC設計と製品アプリケーションにおけるイノベーションを加速させ、現代社会におけるICの普及を促進し、私たちの生活を向上させています。
特に、日本においては、子会社であるJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)を通じて、日本の半導体エコシステム強化に貢献しています。JASMは、日本の半導体技術者不足に対応するため、次世代エンジニアの育成に力を入れています。熊本大学などの大学と提携し、奨学金、インターンシップ、実践的な研究機会を提供することで、学生が最新技術を使った実際の経験を積むことを支援しています。また、定期的なワークショップを通じて、エンジニア、大学の研究者、TSMCのパートナーが集まり、意見交換や技術課題への取り組みを促進し、継続的な学習を支援しています。
長期ビジョンと社会への影響
TSMCは、長期的な視点に立ち、持続可能な成長と社会への貢献を目指しています。その経営理念には、「長期展望と戦略の重要性の認識」が含まれており、「人は遠きを慮らねば、必ず近きに憂いが生じる」という諺を深く信じ、長期的な経営方針に基づいた戦略の立案と実行が最善の危機管理につながると認識しています。
財務面では、2004年より配当を開始して以来、一株当たりの配当金が減額されたことはなく、年間および四半期ベースで安定した配当を確保することで、株主へのコミットメントを果たしています。
TSMCは、その技術と製品を通じて、AI、5G、デジタルトランスフォーメーション、電子機器における半導体コンテンツの増加といったメガトレンドを牽引し、世界の半導体市場の成長に貢献しています。また、大量の電力を消費する一方で、同社が生産する半導体によって世界のユーザーはその4倍の電力使用を節減できると述べており、環境負荷低減にも貢献しています。
このように、TSMCは技術革新、堅実な経営、そして社会貢献への強いコミットメントを通じて、現代社会のデジタル化を支え、未来の技術的進化を牽引する「巨人」としての役割を今後も果たし続けるでしょう。




