記事公開日
最終更新日
TSMC研究三部作:世界の半導体を支える巨人の深奥に迫る(第一部)
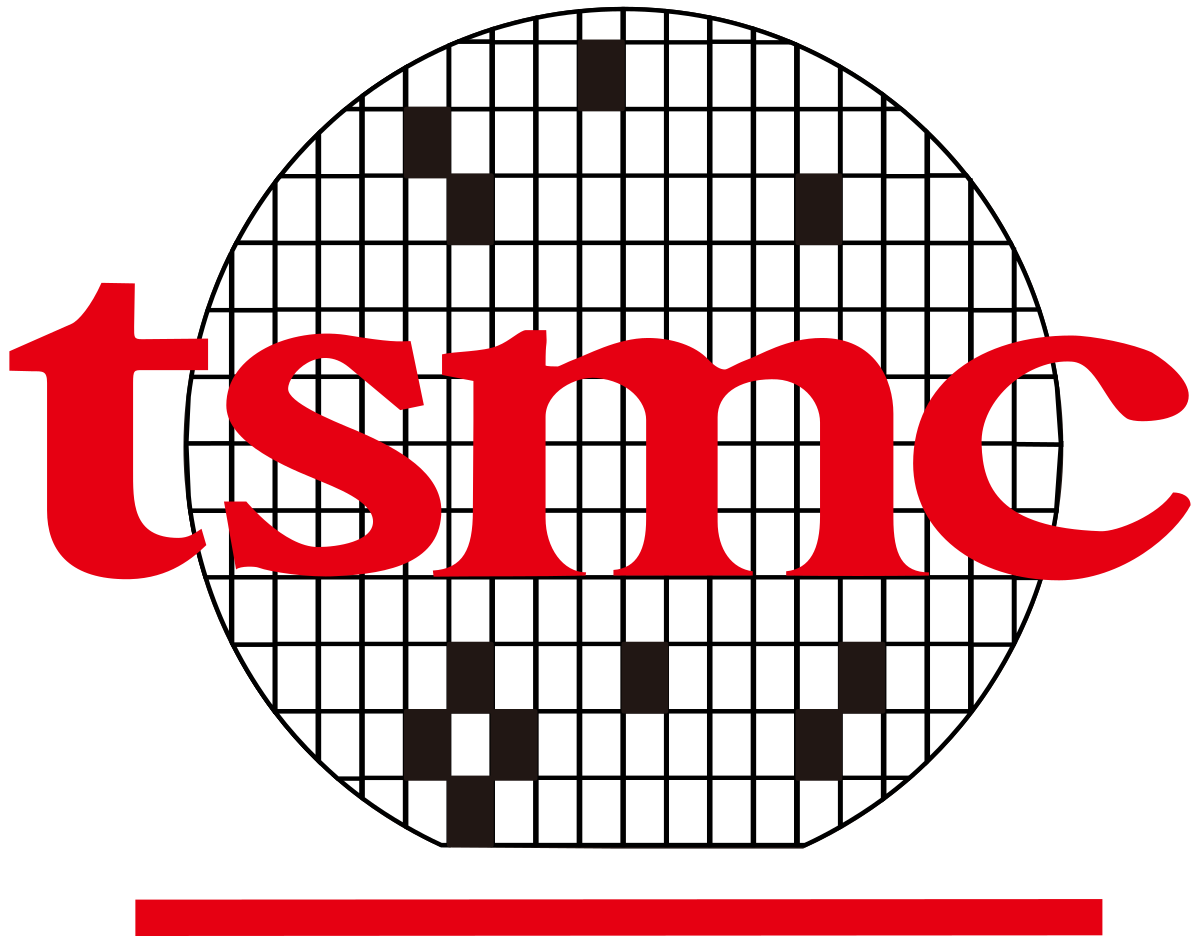
TSMC研究:世界を動かす半導体巨人の全貌
第一部:TSMCの軌跡:半導体産業の礎を築いた巨人
はじめに:現代社会を支えるTSMCの存在
現代のデジタル化された社会において、半導体はまさにその心臓部を形成しています。スマートフォンから人工知能(AI)システム、自動運転車、そして大規模なデータセンターに至るまで、あらゆる最先端技術の根幹には高性能な半導体の存在が不可欠です。この半導体産業において、台湾積体電路製造(TSMC)は、単なる一企業という枠を超え、世界のテクノロジーエコシステムを支える基盤的な役割を担っています。TSMCは、独自のビジネスモデルと卓越した技術力によって、半導体産業の構造そのものを変革し、今日のデジタルイノベーションを牽引する「巨人」として君臨しています。その足跡を辿ることは、現代社会の技術的進化の裏側にある重要な物語を解き明かすことに他なりません。

第1章:創業の精神とファウンドリモデルの誕生
TSMCの設立は、半導体産業における画期的な転換点となりました。その誕生は、台湾政府の先見的な産業育成戦略と、モリス・チャン氏の革新的なビジネス構想が融合した結果として位置づけられます。
台湾政府とフィリップスの共同事業としての設立
1987年、TSMCは台湾政府とフィリップスエレクトロニクスのジョイントベンチャーとして設立されました。当時の台湾は、半導体産業をゼロから立ち上げようとする初期段階にあり、この設立は国家的な産業育成戦略の重要な一環でした。政府は、将来の経済成長の鍵を握るハイテク産業の育成に強い意欲を持っていました。
モリス・チャン氏の先見の明と「ファウンドリ」ビジネスモデルの確立
TSMCの創業者であるモリス・チャン(張忠謀)氏は、半導体業界の未来を鋭く洞察していました。彼は、電子機器メーカーがコスト削減と効率化のために、半導体の製造能力を外部に委託するようになるという趨勢を見抜きました。この洞察に基づき、チャン氏は世界で初めて、集積回路(IC)の製造に特化した「ファウンドリ」というビジネスモデルを確立しました。この専業ファウンドリモデルは、半導体の設計と製造を明確に分業させることで、設計に特化した企業(ファブレス企業)が設備投資の重い製造ラインを持たずに、自由にイノベーションを追求できる環境を創出しました。これにより、半導体業界全体のイノベーションが劇的に加速されることとなりました。
工業技術研究院(ITRI)とRCAからの技術導入の重要性
TSMCの設立に先立つこと十数年前、台湾政府は半導体技術の基礎を築くための重要な布石を打っていました。1972年には、韓国の成功事例に触発された当時の経済部長、孫運璿氏の尽力により、工業技術研究院(ITRI)が設立されました。ITRIは、台湾の半導体産業の黎明期において中心的な役割を担い、特に1976年にはアメリカのRCA社からCMOS型IC製造技術の移転を受けました。この技術移転は、設計、ウェハー製造、封止、検査技術を含む包括的なものであり、台湾の技術者たちはRCAのパイロットプラントでの実習を通じて、最先端の半導体製造ノウハウを習得しました。
このRCAからの技術導入とITRIでの経験は、TSMCが設立される際の強固な技術的土台となりました。TSMCの成功は、単にモリス・チャン氏の革新的なビジネスモデルの着想だけでなく、台湾政府が長期的な国家戦略として、ITRIを通じて半導体技術の獲得と人材育成に先行投資し、強固な技術基盤を築いたことに深く根差しています。政府による初期の技術導入とインフラ整備が、後の民間企業による世界的成功を強力に後押しした典型的な事例と言えるでしょう。モリス・チャン氏の先見の明と、政府による周到な産業育成策が相乗効果を生み出し、TSMCという半導体巨人の誕生を可能にしたのです。
第2章:圧倒的な市場支配力と競争優位性
TSMCは、その革新的なビジネスモデルと継続的な技術革新によって、世界の半導体ファウンドリ市場において圧倒的な地位を確立しています。その市場支配力は、競合他社との比較において顕著であり、顧客からの揺るぎない信頼に支えられています。
世界のファウンドリ市場におけるTSMCのシェア推移
2024年第4四半期において、TSMCは世界のファウンドリ市場で67.1%という圧倒的なシェアを占め、その独占的地位をさらに強化しました。これは前四半期の64.7%からさらに拡大した数値であり、TSMCの一人勝ち状態が続いていることを明確に示しています。
以下の表は、2024年第4四半期における世界の主要ファウンドリ企業の市場シェアを示しています。
| 企業名 | 市場シェア (%) |
|---|---|
| TSMC | 67.1 |
| Samsung | 8.1 |
| SMIC | 5.5 |
| UMC | - |
| GlobalFoundries | - |
| Huahong Group | - |
| (その他) | (合計で残りのシェア) |
注:UMC、GlobalFoundries、Huahong Groupの具体的なシェアは提供された情報にはありませんが、ランキングは固定化しています。
このデータは、TSMCが市場において圧倒的な存在感を示し、そのシェアがさらに拡大している状況を裏付けています。
Samsung、Intelなど主要競合との比較とTSMCの技術的リード(EUV、歩留まり率)
TSMCの主要な競合であるSamsungやIntelも、最先端プロセスの開発に注力していますが、TSMCは依然として技術的リードを保っています。
Samsungはファウンドリ市場で2位に位置するものの、2024年第4四半期には市場シェアが8.1%に急落し、TSMCとの差は59ポイントにまで拡大しました。この背景には、Samsungが3nmプロセスでの歩留まり問題に直面し、これが新規顧客獲得の不足に繋がっていることが指摘されています。
一方、Intelは「Intel 18A」プロセスでTSMCのN2やSamsungのSF2を上回る性能スコアを示唆する評価も存在し、その技術的ポテンシャルは注目されています。しかし、Intelにとっては、この技術を安定的に量産し、高歩留まりを達成できるかが今後の大きな課題となります。
TSMCの技術的リードは、特にEUV(極端紫外線)露光装置の導入と、その高い歩留まり率に顕著に表れています。TSMCは、線幅10nm未満の先端半導体製造に不可欠なEUV露光装置を世界に先駆けて量産に導入し、IntelやSamsungをリードしてきました。さらに、2nmプロセス(N2)では、次世代トランジスタ構造であるGAAFET技術を導入していますが、その歩留まり率は既に量産の目安とされる60%を超え、65%に達していると報じられています。これは、GAAアーキテクチャの初期導入としては驚異的な数字であり、TSMCの圧倒的な技術開発力と製造ノウハウの厚みを示しています。
以下の表は、主要ファウンドリの2nm級プロセスにおける歩留まり率の比較です。
| 企業名 | プロセスノード | 現在の歩留まり率 (%) |
|---|---|---|
| TSMC | N2 | 65 |
| Intel | 18A | 55 |
| Samsung | SF2 | 約40 |
注:歩留まり率は変動する可能性があります。
この比較から、TSMCの圧倒的な市場シェアは、単に最先端技術を開発する能力だけでなく、その技術を早期に、かつ高歩留まりで安定的に量産できるという製造能力に裏打ちされていることが分かります。Samsungが歩留まり問題で顧客を失う中で、TSMCの高歩留まりは顧客にとって極めて魅力的な要素であり、これが市場シェア拡大の直接的な要因となっています。半導体製造における微細化競争は、単にナノメートル単位の数字を追求するだけでなく、その微細なプロセスでいかに経済的に実行可能な歩留まりを達成するかが重要であり、TSMCはこの点で競合他社に一日の長があると言えるでしょう。顧客からの信頼は、技術的な優位性だけでなく、安定した供給と予測可能なコストを実現する運用上の卓越性によって築かれているのです。
なぜTSMCが選ばれるのか:顧客とのパートナーシップとエコシステム
TSMCが世界の主要テクノロジー企業から選ばれ続ける理由は、その「信頼と安定」を重視する哲学と、顧客との強固なパートナーシップ、そして包括的なエコシステムの構築にあります。AppleやNVIDIAといった世界を牽引するテック企業は、TSMCの主要な顧客であり、世界の最先端チップの約90%をTSMCが生産している状況です。
顧客は、TSMCの技術的リーダーシップと卓越した製造技術に揺るぎない信頼を置いています。TSMCは、単に顧客の設計図通りにチップを製造するだけでなく、製品設計を可能にするエコシステムを提供し、半導体産業全体のイノベーションを推進しています。この緊密な連携と、常に顧客の成功を自社の成功と捉える姿勢が、TSMCの競争優位性の源泉となっています。
第3章:グローバル戦略と地政学的リスクへの対応
近年、地政学的緊張の高まりとサプライチェーンの脆弱性が顕在化する中で、TSMCは従来の台湾集中型生産戦略から、世界各地への工場展開へと舵を切っています。これは、経済合理性と国家安全保障の間の新たなバランスを模索する、TSMCにとって重大な戦略転換を意味します。
台湾集中型から世界各地への工場展開(米国、日本、ドイツ)
これまでTSMCは、効率性を最大限に追求するため、工場を台湾に集中的に建設してきました。台湾に集積されたサプライチェーンは、高度な技術連携と迅速な問題解決を可能にし、経済的に極めて合理的な選択でした。しかし、近年、特に台湾海峡の不安定化に象徴される地政学的リスクの高まりと、各国政府からの半導体サプライチェーン強化の要請を受け、TSMCは戦略の見直しを迫られました。その結果、米国、日本、ドイツへの工場建設を相次いで決定しています。
このグローバル展開は、TSMCにとって重大な戦略転換です。台湾での生産が最も効率的であるという認識は変わらないものの、有事の際のリスクを考慮し、一定の効率性を犠牲にしてでも生産拠点を分散させる必要性を認識したことを意味します。また、台湾における土地、水、電力、人材といった資源の制約も、海外展開を後押しする要因となっています。
サプライチェーンのレジリエンス強化と国家戦略との連携
米国、日本、ドイツへの工場建設は、グローバルサプライチェーンの脆弱性、特にコロナ禍での停滞や地政学的リスクへの対応として位置づけられます。この分散化戦略は、サプライチェーンのレジリエンス(強靭性)を劇的に向上させ、不測の事態が発生した際のリスクを大幅に低減する効果が期待されます。
特に米国では、TSMCのアリゾナ工場で2nm世代の最先端チップが生産される計画であり、これは米国の半導体製造能力を世界最先端レベルに引き上げるという国家戦略と合致しています。米国政府は「CHIPS and Science Act」を通じて巨額の補助金を提供し、TSMCの投資を強力に後押ししています。これにより、アリゾナ工場は単なる生産拠点に留まらず、先進パッケージング施設や研究開発センターも含む「半導体メガクラスター」へと進化し、米国内のAIサプライチェーンを完成させる役割を担うことになります。
日本においても、TSMCはソニー半導体、デンソー、トヨタ自動車との共同出資により熊本県にJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)を設立しました。JASMの工場は、日本の半導体製造基盤を強化し、国内の産業競争力向上に貢献することを目指しています。このように、TSMCの海外工場建設は、単に生産能力を増強するだけでなく、各国の国家安全保障や産業育成戦略と深く連携し、グローバルなサプライチェーンの再編を促す重要な動きとなっています。
海外投資に伴う課題(コスト、技術移転、人材確保)
TSMCのグローバル展開は戦略的な意義を持つ一方で、いくつかの重要な課題も伴います。まず、海外での製造コストは台湾と比較して著しく高く、これが最終的な製品価格に反映される可能性があります。例えば、米国アリゾナ工場のコストは台湾の4~5倍に達するとも言われています。
次に、半導体製造は極めて複雑な技術であり、熟練した技術者の確保と技術ノウハウの海外拠点への円滑な移転は容易ではありません。特に、長年にわたって台湾で培われてきたサプライチェーンのエコシステムや技術者の知見を、短期間で海外に再現することは大きな挑戦です。
さらに、海外工場進出は現地の人材市場にも大きな影響を与えます。例えば、日本の熊本では、TSMCの進出により地元企業からの人材流出や賃金上昇が懸念されています。TSMCのような大企業は、競争力のある給与や福利厚生を提供するため、地元の中小企業は優秀な人材の確保に苦慮する可能性があります。この課題に対応するため、熊本では地元大学との連携による人材育成プログラムの推進や、外国人労働者の活用、地域全体での働きやすい環境整備など、多角的な対策が求められています。
これらの課題は、TSMCがグローバル戦略を推進する上で克服すべき重要な障壁であり、経済合理性と地政学的リスクのバランスを取りながら、持続可能な成長を実現するための鍵となります。

編集者: マイソリューションズ編集部 https://hr.my-sol.net/contact/



