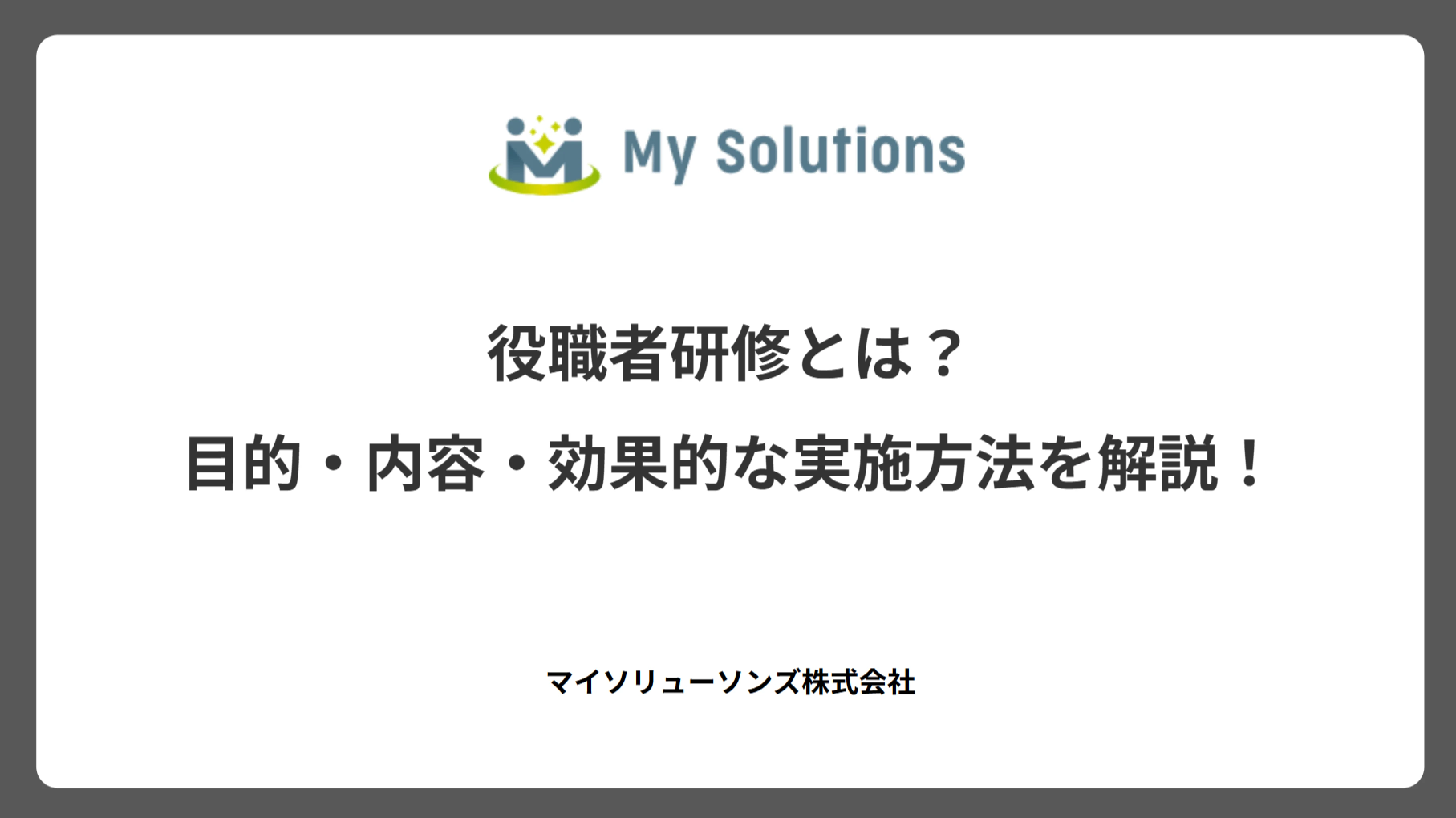記事公開日
最終更新日
オードリー・タンに学ぶ、会社の「会議」と「意思決定」を変える方法 パート3
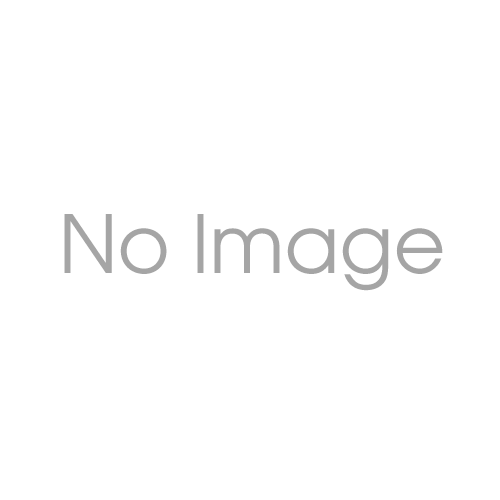
明日からできる!オードリー・タン流「最強のチーム」の作り方
これまでの分析を踏まえ、オードリー・タン氏の教えからヒントを得た、新しい企業内合意形成のフレームワークを提案します。これは、従来の指示命令型の組織に代わる、学習と適応を重視した、新しい組織のOS(オペレーティングシステム)です。
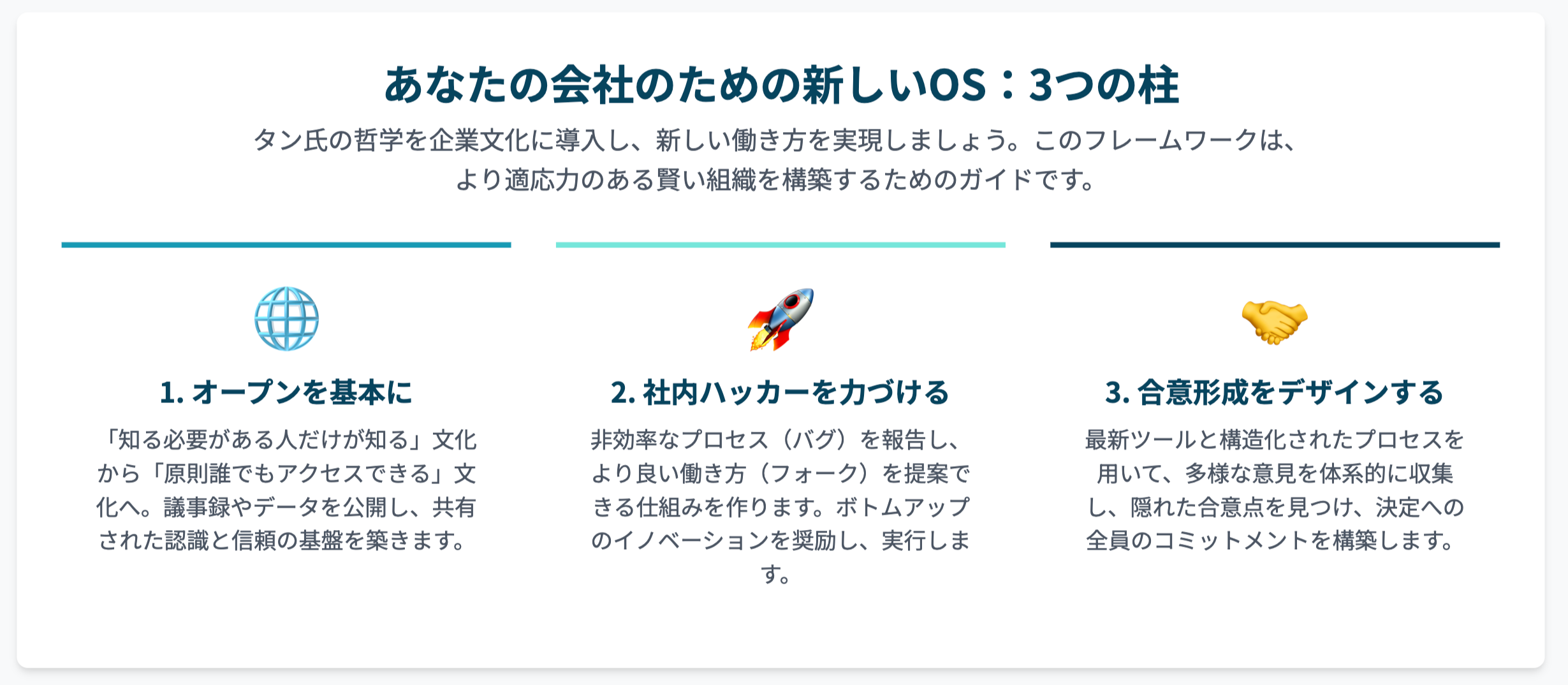
第1の柱:「情報は隠さない」が当たり前の文化を作る
組織内の情報フローを根本から変革し、「知る必要がある人だけが知る」から「原則、誰でもアクセスできる」へと文化をシフトさせます。
- 具体的なアクション: プロジェクトの資料、会議の議事録(AIによる自動文字起こしツールの活用がおすすめ)、主要な業績データなどを、全社員が見られる場所に保存することをルールにします。Slack社のように、経費や福利厚生に関する質問をオープンなチャンネル(例:
#経理相談)で行うことで、知識が特定の人に偏るのを防ぎ、組織全体の知恵として蓄積していくのも効果的です。
第2の柱:「コーポレート・シビックテック」― 全員が改善の主役になる
g0vの「ないなら、作っちゃえ!」精神を会社に導入し、全社員を組織のプロセスを良くしていく改善者として位置づけます。
- 具体的なアクション: 社内SNSやチャットツール上に、非効率なプロセス(バグ)を報告したり、もっと良い働き方(フォーク)を提案したりできる専用の場所を作ります。g0vのハッカソンを真似て、社員が主導する改善案を素早く試作し、テストするための社内イベントを定期的に開催するのも良いでしょう。リクルート社の新規事業提案制度「Ring」なども、この考え方に近い取り組みです。
第3の柱:みんなの声を「科学的に」聴き、合意点を見つけ出す
vTaiwanとPol.isの仕組みを応用し、たくさんの多様な社員の意見を体系的に集め、納得感のある合意へとつなげます。
- 具体的なアクション: 全社に影響が大きい、あるいは部署間で意見が対立しやすい重要なテーマ(例:新しい人事制度の導入、中期経営計画の策定、リモートワークの方針など)の意思決定に、Pol.isのような意見マップツールを導入します。vTaiwanの4段階プロセスを参考に、幅広いアイデア出しから具体的な合意形成まで、議論のプロセスをデザインします。
表で見る:これからの合意形成はこう変わる!
このフレームワークがもたらす変化を、下の表にまとめました。これまでの組織と、私たちが提案する「ラディカル・トランスパレンシー組織」の根本的な違いが一目でわかります。
| 比較ポイント | 従来型の指示命令モデル | ラディカル・トランスパレンシー・モデル(タン氏の教え) |
|---|---|---|
| 情報の流れ | タコツボ化、階層的、「知る必要がある」が原則 | 原則オープン、ネットワーク型、誰でもアクセス可能 |
| 意思決定の基準 | 役職や権威、多数決、経験と勘 | データに基づき、「なんとなくの合意」を探し、みんなの知恵を活かす |
| 対立の扱い方 | 避ける、抑え込む、偉い人に判断を委ねる | 意見の違いを歓迎し、共通点を探し、対立から新しいものを生み出す |
| 社員の役割 | 受動的な実行者、「指示待ち」 | 能動的な問題解決者、プロセスの改善者、「社内ハッカー」 |
| リーダーの役割 | 司令官、決定者、門番 | 進行役、プロセス管理者、「パイプ役」 |
| 成功の指標 | 決定の速さ、指示が守られているか | 成果の質、みんなの納得度、組織として学べたか |
3つのステップで変革する!デジタル民主主義への道すじ
この変革は、単に新しいツールを導入すれば終わり、というものではありません。組織の文化やリーダーのあり方を根本から変える旅のようなものです。そのためには、焦らず、段階的かつ戦略的に進めることが大切です。
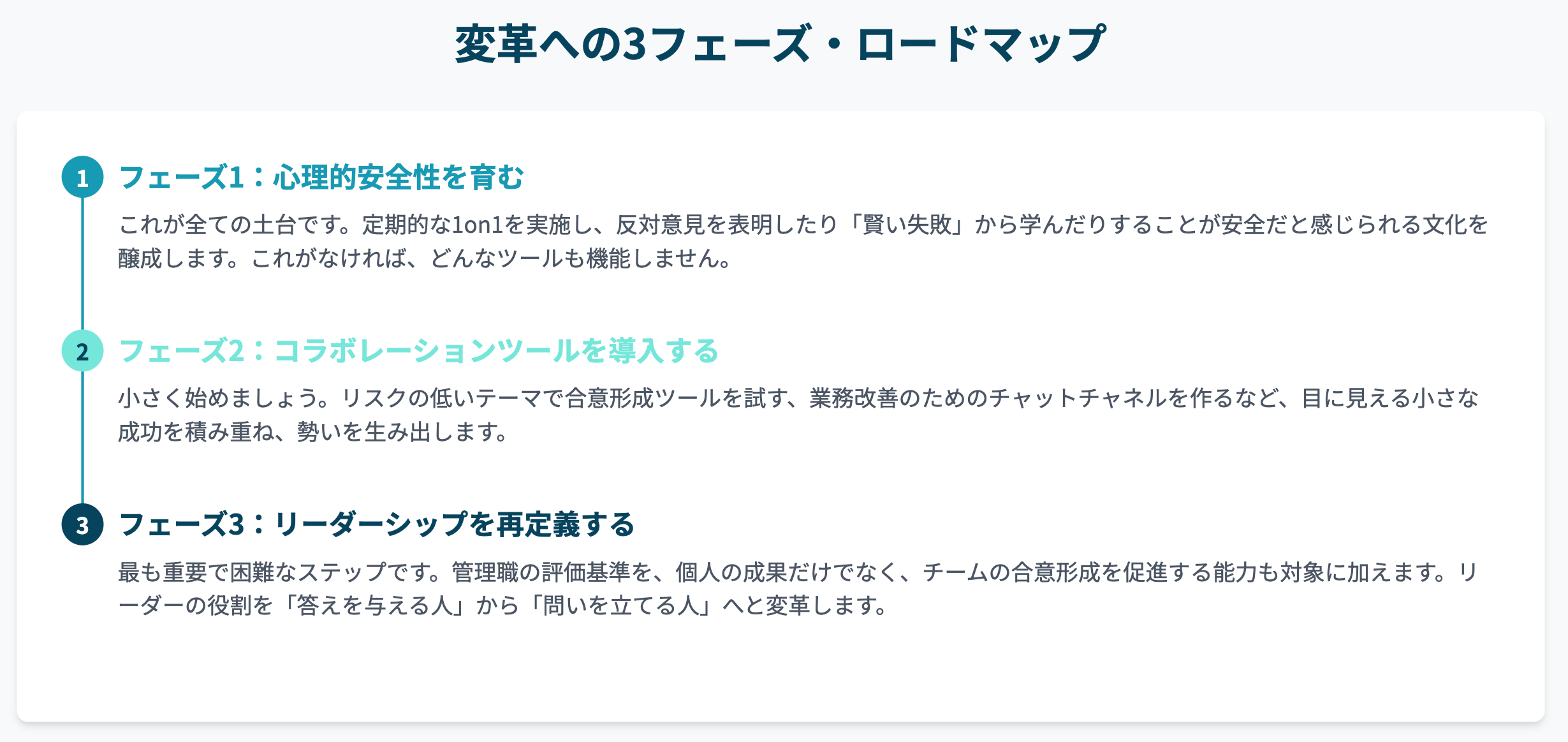
フェーズ1:何でも言える「心理的安全性」を育む ― すべての土台作り
どんなに素晴らしいツールやプロセスも、社員が「こんなこと言ったら怒られるかも…」と恐れていては機能しません。自由に発言し、現状に疑問を投げかけ、失敗を恐れずに挑戦できる環境、すなわち「心理的安全性」が、この変革の最も重要な土台です。
- アクションプラン:
- 上司と部下が1対1で対話する「1on1ミーティング」を定期的に行い、仕事の評価だけでなく、キャリアやプライベートな関心事についてもオープンに話せる関係を築きましょう。
- 管理職向けに、部下の話をじっくり聴き、建設的なフィードバックをするためのトレーニングを実施します。
- 失敗を罰するのではなく、そこから得られた学びを共有し、称賛する「賢い失敗(インテリジェント・フェイラー)」の文化を育てましょう。Googleやメルカリなど、心理的安全性を重視する企業の事例が参考になります。
フェーズ2:便利なツールで変革を後押しする ― テクノロジーの導入
文化的な土台を築きながら、変革をスピードアップさせるためのテクノロジーを少しずつ導入していきます。
- アクションプラン:
- まずは小さなプロジェクトから始めましょう。例えば、会社の根幹に関わる問題ではなく、社内で意見が分かれがちなテーマ(例:社内イベントの企画)でPol.isを試験的に導入し、その効果をみんなで体験してみます。
- 特定の部署やチームで、SlackやMicrosoft Teams上に「業務改善ハッカソン」チャンネルを作り、ボトムアップでの改善活動を応援します。
- AsanaやJiraのような、進捗が「見える化」されるプロジェクト管理ツールを導入し、誰が何をやっているのかを関係者全員が把握できるようにします。大切なのは、小さな成功体験を積み重ね、組織全体に「やればできる!」という勢いを生み出すことです。
フェーズ3:リーダーは「答えを出す人」から「答えを引き出す人」へ
これは最も難しく、そして最も重要なステップです。管理職の役割を、答えを与える「専門家」から、チームの中から最高の答えを引き出す「進行役(ファシリテーター)」へと変えていく必要があります。
- アクションプラン:
- 管理職の評価基準を見直します。個人の成果だけでなく、チームの協力を促し、質の高い合意形成を導いたかを評価の対象に加えます。
- リーダーシップ研修の内容を刷新し、意思決定プロセスのデザイン、多様な意見の引き出し方、対立を建設的に解決するスキルなど、ファシリテーション能力の向上に重点を置きます。
こんな風に変わる!具体的な応用シナリオ
このフレームワークが、実際のビジネスシーンでどのように機能するのか、2つのシナリオで見てみましょう。
- シナリオA:会社の次期戦略を立てる
- シナリオB:部署をまたぐ新プロジェクトの承認プロセス
- これまで: 関係部署への根回しや、声の大きい部署の意見が優先されるなど、政治的なプロセスが横行。承認までに数ヶ月かかり、なぜ承認されたのか(されなかったのか)の基準も曖昧。
- これから: プロジェクトの提案を、全社で共有されるプラットフォームに投稿。提案書には、事前に決められた透明な評価基準(会社の戦略と合っているか、費用対効果はどうかなど)に沿った情報を記載します。関係者はプラットフォーム上でオープンに質問したり議論したりします。これにより、プロセスは速く、公平になり、政治的な駆け引きが入り込む余地が大幅に減ります。
おわりに:未来の会社は「聴く組織」になる
この記事で見てきたオードリー・タン氏が台湾で実践してきたことは、単なるユニークな政治実験ではありません。それは、21世紀の組織を作るための、強くてしなやかな設計図です。これからの時代、企業の競争力は、もはやトップの指示命令の速さからは生まれません。それは、競合他社よりも速く学習し、変化に対応し、そして組織全体の知恵を結集する能力にかかっています。
このモデルが最終的にもたらすのは、「傾聴する組織(Listening Organization)」の実現にあります。社員の声に、お客様の声に、そして市場の声に、組織全体で真剣に耳を傾けることができる会社。それこそが、どんな環境変化にもしなやかに対応し、あらゆるチャンスを掴むことができる、自己進化する組織の姿です。この記事で提案したフレームワークが、あなたの会社を硬直した機械から、生命力あふれる生命体へと変えるための、具体的な第一歩となれば幸いです。
パート2はこちら→ https://hr.my-sol.net/media/useful/a130
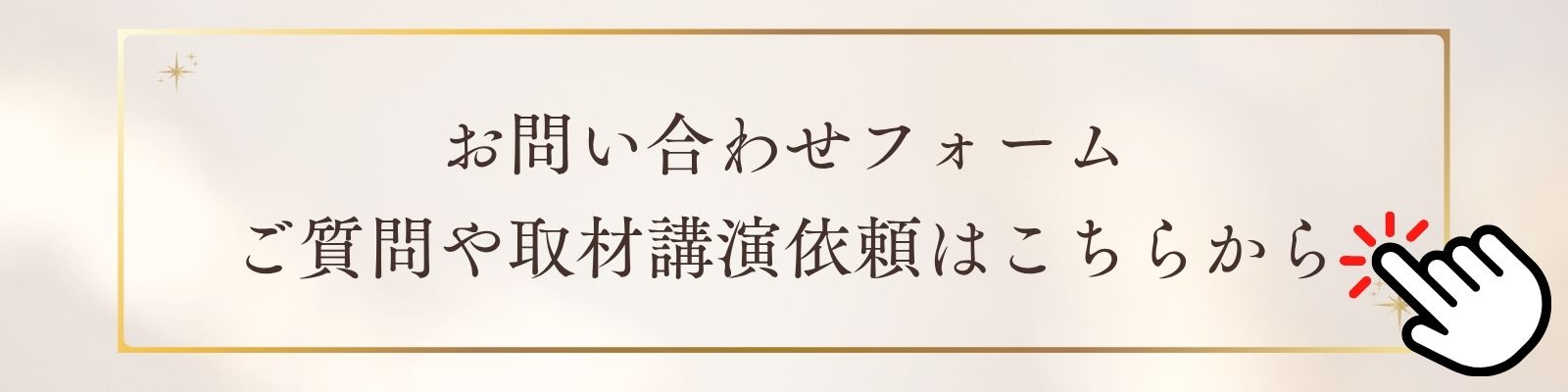
編集者: マイソリューションズ編集部 https://hr.my-sol.net/contact/
マイソリューションズでは、本記事のような企業内合意形成のノウハウをはじめ、多岐にわたる研修実績やコラムを定期的にご紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。 https://hr.my-sol.net/media/useful/